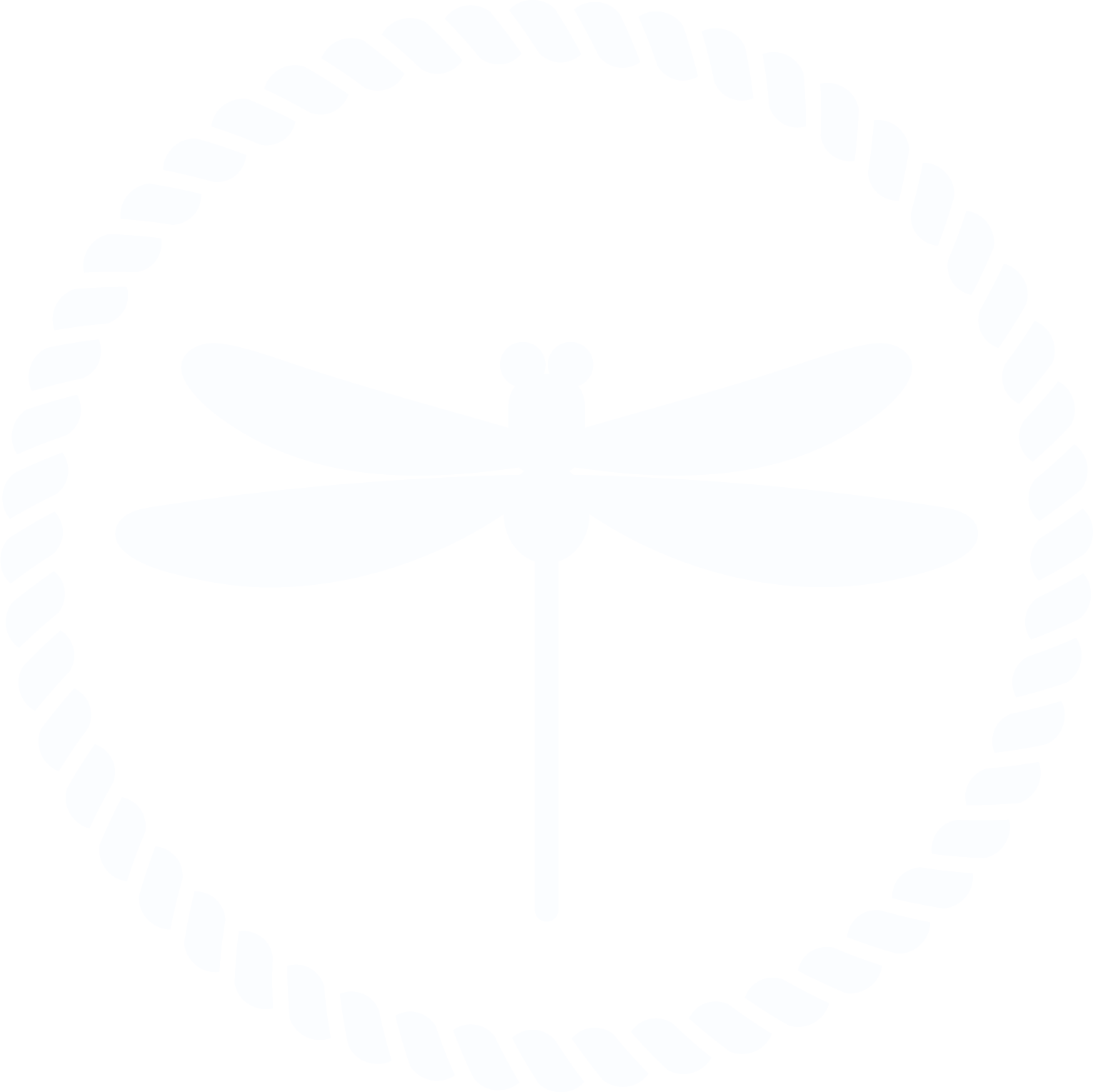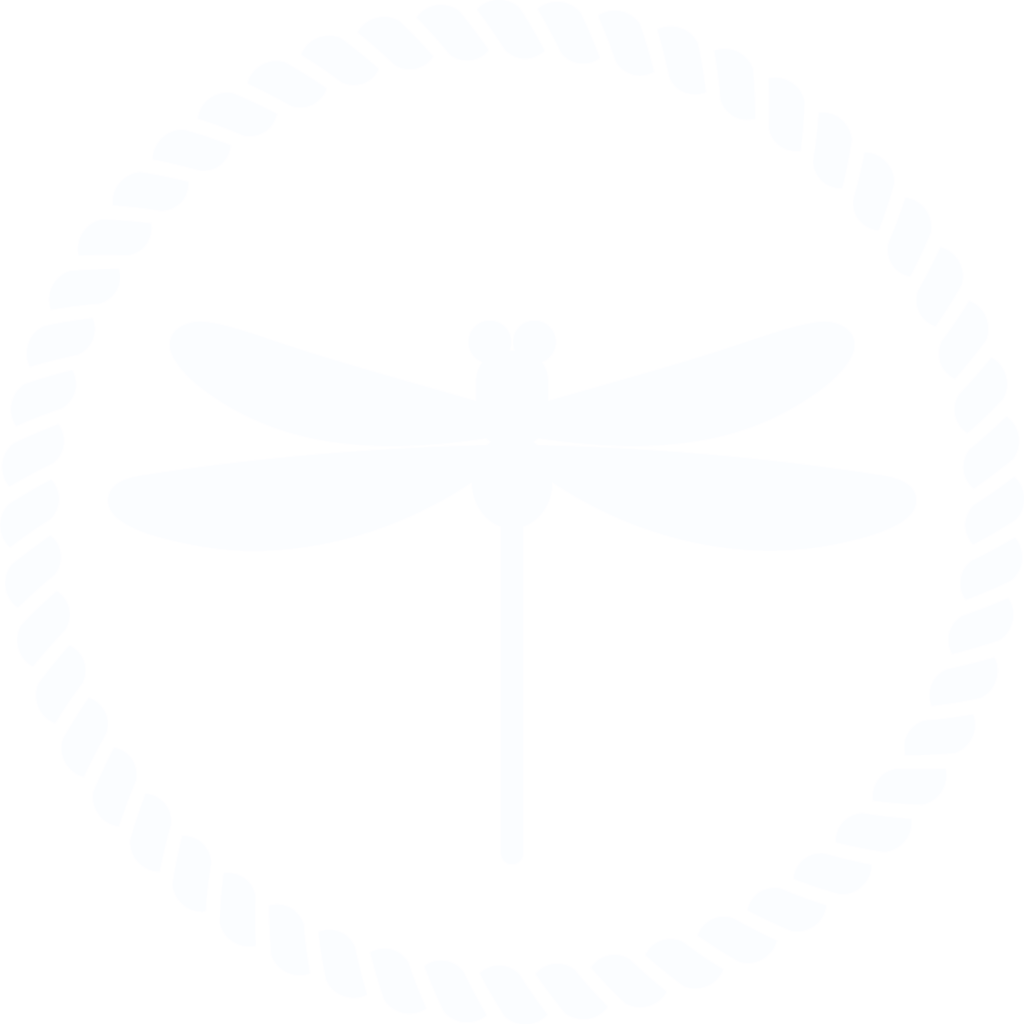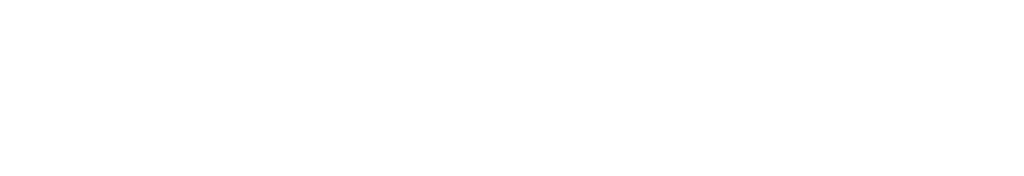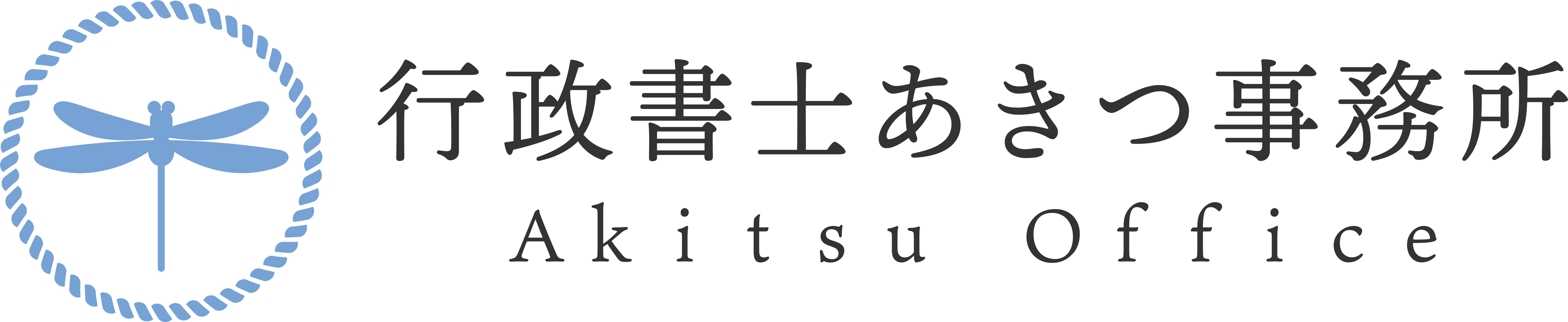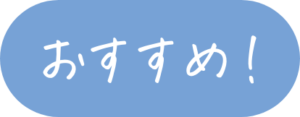「日本人の配偶者等」ビザの特徴と注意点

日本人の配偶者等ビザの概要
日本人の配偶者等ビザとは何か?
日本人の配偶者等ビザは、外国籍の方が日本人と婚姻した場合などに、日本国内に長期的に滞在し生活するための在留資格です。日本人と外国籍の方がお互いの国で必要な入籍手続きを行なっただけでは、外国籍の方が、日本に長期間滞在することができません。
そのため、国際結婚をしていることを前提として、それが真実の婚姻であることを法務省出入国在留管理庁に対し、説明・立証し、日本に滞在し生活するための在留資格を取得することが必要です。
日本人の配偶者等ビザがどういうものなのか、また許可取得後のメリットや注意点などをご説明していきます。
在留資格「日本人の配偶者等」の種類
在留資格「日本人の配偶者等」には、三つの状況が含まれています。
その中身は、①日本人の配偶者、②日本人の特別養子、③日本人の子として出生した者、の三つをいいます。
- 日本人の配偶者は、それぞれの母国において婚姻手続きを行い、法律上の婚姻をし、夫又は妻となった外国籍の方をいいます。
- 日本人の特別養子は、家庭裁判所において、原則15歳未満が行う養子縁組のことで、実の両親との戸籍上の親子関係を断ち、日本人の養親に扶養されて生活していく外国籍の方をいいます。
- 日本人の子として出生した者とは、日本人の実の子です。これは子の出生の時に、父又は母が日本国籍を有していることが必要です。婚姻関係に無い両親から生まれた場合、「認知された子」であればこのケースに該当します。
日本人の配偶者等ビザのメリット
日本人の配偶者等ビザの目的は、多くは日本人の配偶者や子として日本で生活することです。
就労の必要はない。日本人の夫や妻などによって、生活が成り立っているのならば働く必要はありません。
職業の選択に制限がありません。これが身分系資格と他の就労資格と大きく異なる点です。日本人が就職したり、アルバイトに応募したり、会社を経営したりするのと同じように仕事を選択することができます。
「留学」の在留資格をせずに、大学などに通い学ぶことができます。
永住申請や帰化申請をする際の条件が緩和される。
永住申請について、要件の中に、原則10年以上の在留が必要となっていますが、日本人・永住者・特別永住者の配偶者である方は、婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば永住申請の条件をクリアします。
また日本人の子や養子の場合は、1年以上日本に継続して在留していれば永住申請の対象となりえます。
帰化については、国籍法5条で、成人(18歳以上)で、引続き5年以上日本に住所を有することが必要とされていますが、既に日本人の配偶者等ビザの方は、日本人との婚姻生活を鑑みた緩和要件が2つあります。(国籍法7条)
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するもの
例)日本で就労ビザ等の在留資格で働き3年が経過後、日本人と結婚。そのまま日本に生活基盤をもって暮している外国人。(3年以上居住している。現在も日本に住所がある。日本人と婚姻している。)
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し,かつ,引き続き一年以上日本に住所を有するもの
例)海外で日本人と結婚2年経過、その後日本人と共に来日。そのまま日本に生活基盤をもって1年以上暮している外国人。(1年以上居住している。現在も日本に住所がある。日本人と婚姻して3年以上経過している。)
このように日本人と特別な関係をもつ外国人(日本人の配偶者・日本人の子・日本で生まれた子・かつて日本人だった人など)は、今後も日本に根ざして生活をされることを考え、より安定した生活を送ることが出来るよう帰化申請への条件を一部緩和されています。
当然のことながら、日本語能力など他の要件もあり、厳格な審査が行なわれることはいうまでもありません。
申請方法と手続の流れ
申請手続きの流れ
※入管庁への申請書類作成の前に、ご夫婦が国際結婚していることが必要です。
国際結婚の流れは大きく以下のような流れです。
ご夫婦のもう一方の方の母国発行の書類が必要です。
・婚姻具備証明書など
・国際結婚の完了
・法務省出入国在留管理局へ在留資格を申請するために必要な書類を収集・作成します。
※国際結婚の手続については、改めて詳しくご説明します。
外国人配偶者が海外にいる場合のビザ申請の流れ
・在留資格認定証明書を取得します。
(日本への呼び寄せ。これを在留資格認定証明書の交付申請手続きと言います。)
日本在住の日本人配偶者が申請人となり、入管庁に在留資格認定証明書交付申請を行い、審査を受ける。
入管庁の審査結果として、問題なく許可であれば、郵送又はオンラインで在留資格認定証明書を受け取る。
海外にいる外国人配偶者に、郵送又はオンラインで、在留資格認定証明書を送る。
外国人配偶者が母国の日本大使館・領事館で、日本へ行くためのビザ(査証)を申請する。
その査証申請の際に日本で取得した「在留資格認定証明書」も必要となります。(証明書の期限三ヶ月以内。)
外国人の母国の日本大使館等で、ビザ(査証)発行後、日本へ渡航します。(ビザ期限の三ヶ月以内に。)
入国時に空港で上陸審査。(パスポート・在留資格認定証明書提示)
入国後、空港内で在留カードの交付を受け、日本での生活が始まります。
外国人配偶者が日本に滞在中の場合のビザ申請の流れ
既にお持ちの在留資格からの変更申請が必要です。
(これを在留資格変更許可申請手続きと言います。)
① 外国人配偶者が、入管庁に在留資格変更許可申請を行い、審査を受ける。
② 入管庁の審査後許可されれば、「日本人の配偶者等」と記載された在留カードを、入管庁で受け取る。
※「在留資格認定証明書」とは、外国籍の方が、日本国内の、どこで、どのような活動を行なうのかを、来日する前に、日本の法務省の審査を受ける。ということを意味します。
審査後、許可され、在留資格認定証明書が交付されれば、それは法務省の推薦状のような意味を持ちます。
また外国にある日本大使館等は、外務省の管轄であり、外国籍の方が、来日する際に、日本国内へ入国して問題がないかを審査し、ビザ(査証)を発行する権限を持ちます。
外国籍の方が来日する前に、日本国法務省での審査を先に受け推薦状を持っていれば、母国の日本大使館等へのビザ(査証)申請時に、スムーズに手続を受けることが可能です。
ただ、法務省の在留資格認定証明書が事前に交付されていても、外務省日本大使館が、日本への渡航ビザを発行しない判断をすることもできます。
在留カードの交付方法は、主に二つあります。
① 中長期在留者として、初めて来日し、新規の上陸審査許可を受けて、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港 広島空港、福岡空港から入国した場合は、
空港内で在留カードの交付を受けることができます。
② 上記①の空港以外の空港や港から入国した場合。
日本に入国した後、市区町村に住所の届出(転入届)を提出する。
その後、住所地である自宅に在留カードが郵送されます。
配偶者ビザ手続きの注意点
審査のポイント
配偶者ビザを申請する際には、以下のとおりいくつかの注意すべき点があります。
① 国際結婚が真実のものであり、実体が伴っていること。
配偶者ビザについて、入管庁が最も厳しくチェックするポイントは、偽装結婚です。
「日本人の配偶者等」などの身分系の在留資格の許可を得ることで、就労の制限もなくなり、永住や帰化の要件緩和などの恩恵を受けることができます。永住権等の許可を得るまでの間の偽装結婚などということもケースとしてあり、逮捕者も出ています。
② 日本において安定した生計を維持継続できるかどうか。
日本人と結婚をし、日本人の配偶者等のビザを取得後、夫婦で安定して暮らしていくことができる収入や資産があることが重要です。
入管庁も収入水準を明らかにしていませんが、夫婦の合計で、おおよそ20万円ほどの収入、年間240万円~300万ほどあれば生活が出来るのではないかと考えています。これは地域により差があるのであくまでも推測です。
しかしながら、日本人側の両親との同居や、預金や資産が潤沢にある場合、また今後の仕事の収入増加の見込みや計画など決まっていることがあれば、積極的に資料を提出することで、今後生計が成り立つことを証明できれば、許可される可能性はあります。
③ 日本人の配偶者等の申請に際し、「身元保証人」が必要。
通常は、結婚相手である日本人配偶者が身元保証人になり、提出書類「身元保証書」を作成し申請書類のひとつとして提出します。
身元保証の責任内容は、日本での滞在費用、外国人配偶者が帰国する際の費用、外国人配偶者が法律を遵守すること、この三点について道義的な責任を負います。
借金の保証人のような法律上の責任ではありません。
また夫婦の収入が不安定である場合には、安定した収入のある身元保証人を追加することによって、日本での生活安定性への疑念が解消され、入管庁の許可を得られることがあります。一般的には、日本人配偶者の親や兄弟などの親族が考えられるでしょう。
身元保証人が用意する書類は、法務省HPからダウンロードする身元保証書のほか、住民票、収入や納税を証明する公的書類、在職証明書、財高証明等を提出する必要があります。
④ 素行に問題がない。
日本でも、外国でも、法律を犯していないこと、罰則を受けていないことが重要です。
もしある場合は正直に報告する。又はビザ申請のタイミング自体をもう一度考え直すことも必要かもしれません。
不許可の事例
日本人の配偶者ビザの申請が不許可となれば、日本に滞在するための在留資格が無いため、国際結婚したものの、日本人の配偶者として暮らすことができません。
また既に日本人の配偶者等ビザを持っている方は、在留資格の更新が不許可となれば、滞在資格を失うため、帰国をしなければならなくなります。滞在期限が切れる前に他の在留資格への変更などの対策をとらずに滞在を続けていると、不法滞在(オーバーステイ)となり、退去強制手続きとなってしまいます。
さらには、将来永住権を考えている場合、永住権申請に必要な滞在期間も再度来日し、最初からカウントを開始しなければならなくなります。
このように不許可にならないために注意すべき主なポイントを見ていきます。
① 生計を生計を維持できる収入がない、現在無職である
先ほども述べたように、夫婦の収入が少ない場合、預貯金や資産が乏しい場合などは、日本での生活を維持出来なくなり、生活保護を受けなければならなくなったり、生活のため犯罪に手を染めてしまうなど、外国人本人にとっても、日本にとって良くないことが生じる可能性を入管庁は考えています。
生計が維持できるだけの収入がない場合は、今後の転職先の給与の情報や生活を援助してくれる方が身元保証人になっている、預貯金や潤沢が資産があるなど、これからの生活の見通しを根拠資料と共に提出し、入管庁に今後の生計の維持については問題ないようだ。と思ってもらうことが重要です。
② 税金などの滞納がある
日本においての義務である、住民税、国民健康保険税・年金などの社会保障等について、直近2年から3年間は遅れることなく、全て支払いが完了している必要があります。また扶養する家族についても同様です。会社経営者の場合は会社に関する税金の支払いも遅れや未払いがないことを確認しましょう。
これは後々の永住権の申請などにも関わってくる重要なポイントで、日本の義務やルールを守ることが出来ているか?ということを非常に厳しく審査されます。
支払いが遅れている状況があれば、申請不許可となる場合もあるので、支払い金額、支払い期限、また転職時の未払いなど、自分自身が支払うべきものを正確に管理し、遅れが絶対に無いようにすべきです。
③ 離婚歴が多い
離婚歴が多い場合や婚姻期間が短い場合などは、偽装結婚の疑いをもたれてしまいます。前回の申請内容などとの整合性も非常に厳しくチェックされ、追加書類の提出依頼も多くなり、審査期間も長くなります。申請に際しては、最初から偽装結婚ではなく、愛し合っており、真実の結婚である証拠資料を提出し理解していただくことが許可を得るポイントです。
④ 年齢差のある結婚
夫婦の年齢差が大きい場合、例えば日本人男性55歳と外国人女性23歳など、一般的にはとあまり無いケースの場合は、偽装結婚を疑われます。また年齢差の大きさに加え、出会いから婚姻までの期間が短いことも、偽装結婚を疑われ不許可になる要因の一つです。
⑤ 日本語能力・コミュニケーションの方法が現実的ではない
日本人の配偶者等ビザの取得には、外国人配偶者の日本語能力自体は必要ありません。その他の言語によって夫婦間のコミュニケーションが問題なくとれていれば、婚姻の真実性や信憑性を証明することもケースによっては可能です。
お互いの言葉が理解できない状況で、どのように知り合い、交際期間中はどうしていたのかなど、結婚自体に疑念を抱かれるような状況では、不許可になる可能性も高まります。真実の愛であることを証明するために、それを証明するために、わかりやすい資料を準備、提出するようにし、審査官に理解していただくよう心掛けましょう。
また日本人の配偶者等ビザを取得して日本で生活していくのであれば、多くの場面で日本語能力は必ず必要になるものです。日本人配偶者との日本での暮らしのために、日本語学校などで努力を重ねていること、日本語の試験の合格証などの資料と共にアピールすることも方法の一つになります。
⑥ 過去に犯罪歴等がある
在留資格取得に際し、例えば、交通違反、薬物などの犯罪歴があるなど素行が悪い場合、許可の可能性が非常に低くなってしまいます。
例えば、留学生時代に資格外活動許可を得て行っていたアルバイトで、上限の週28時間以上働いてしまい、オーバーワークとなってしまったケース。在留期限が来ても更新や出国せず、いわゆるおオーバーステイ・不法滞在をし、退去強制により帰国した経緯があるケースでは不許可の可能性が高いと思います。
状況によっては1年~5年は日本への入国ができなくなってしまいますので非常に注意が必要です。
まとめ
このように日本人の配偶者等ビザ取得にはメリットも多くありますが、注意すべきことも非常に多くあります。
しかしながら、真実の愛によって国境を越えて愛し合い、国際結婚をされているのであれば、注意すべきポイントをしっかり押さえることで、ビザを取得できる可能性が高くなります。
情報の勘違いなどにより、間違った内容で申請してしまう前に、不明なことや不安に感じることがあれば行政書士など専門家に相談するなどして、確認しながら準備を進めていくことが大切です。