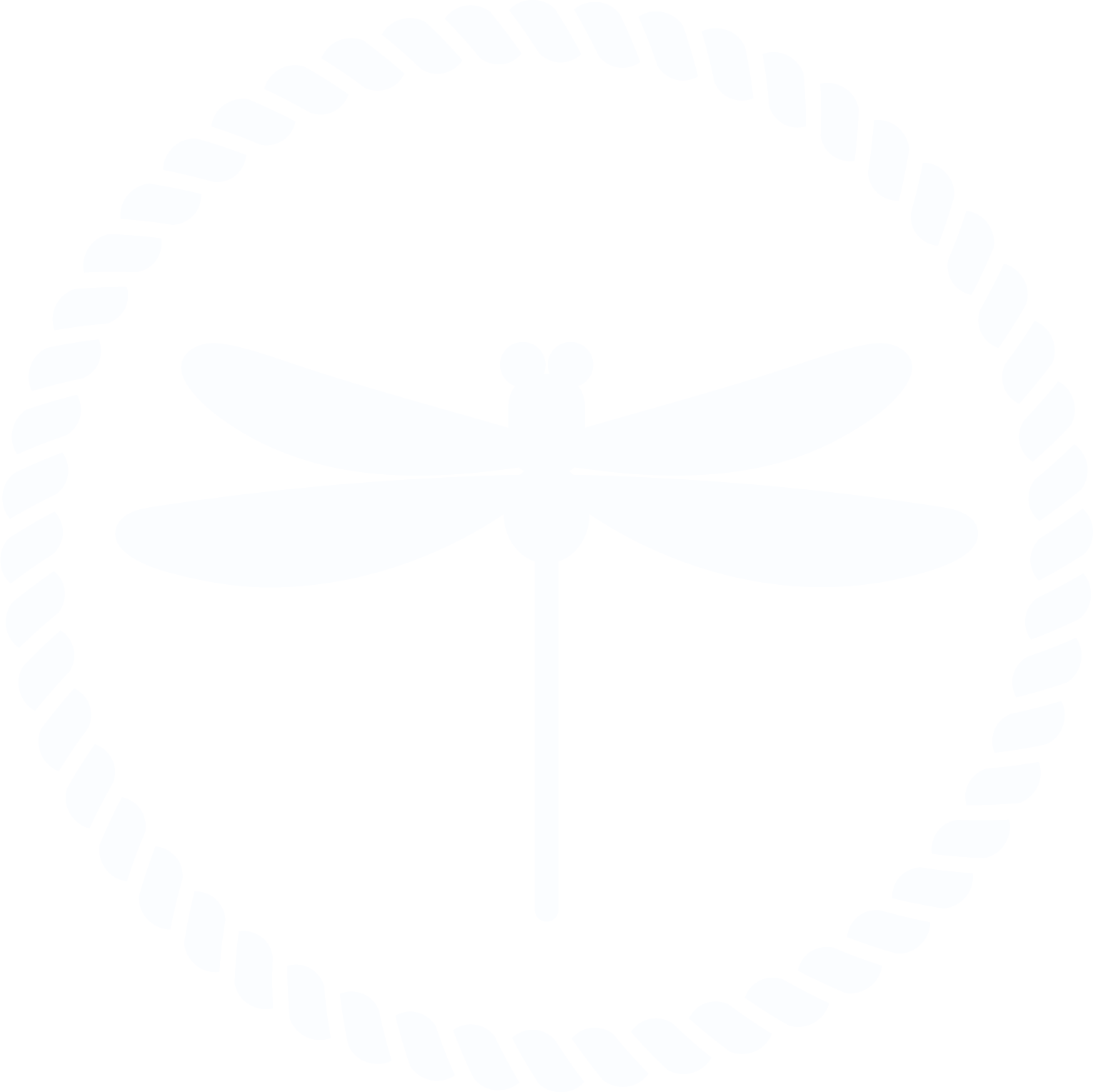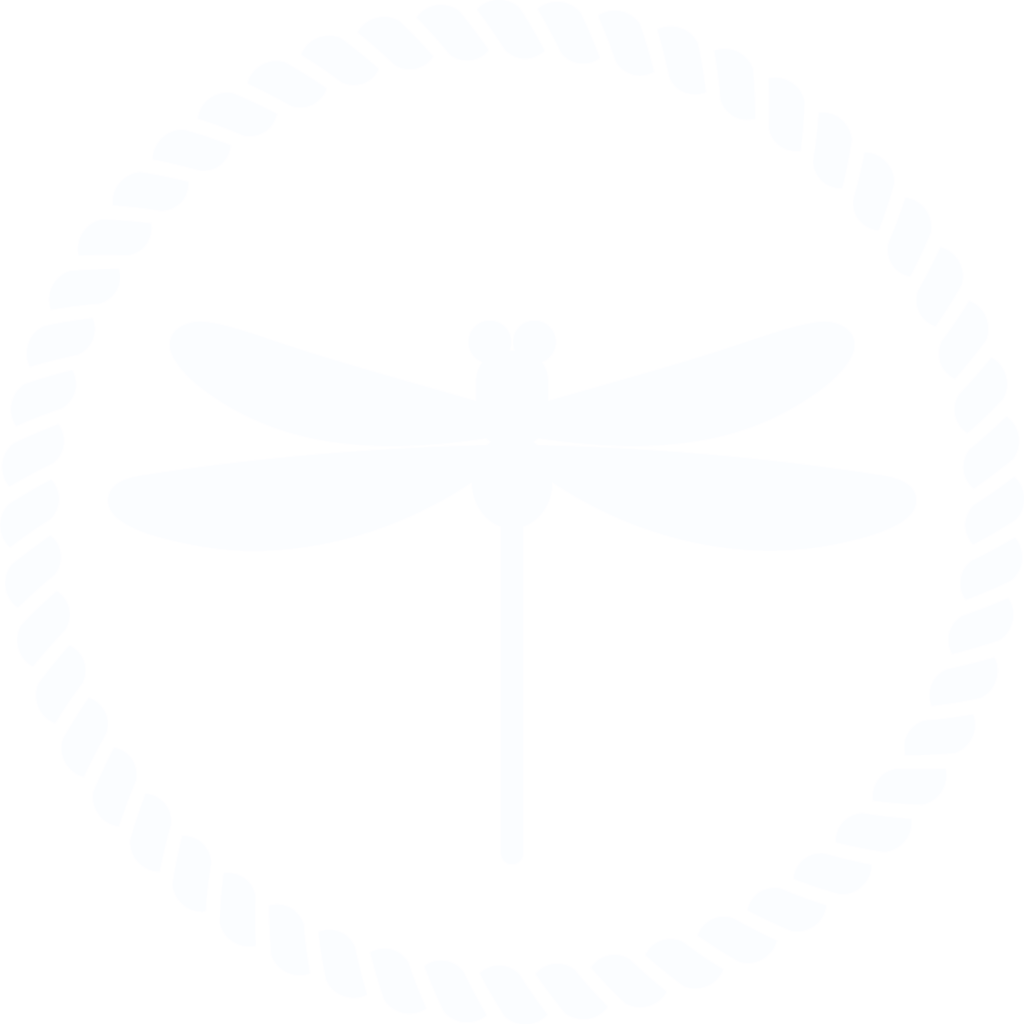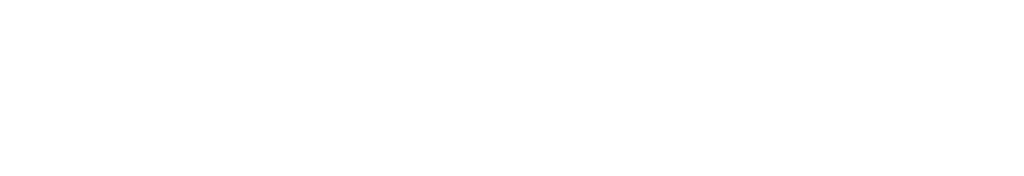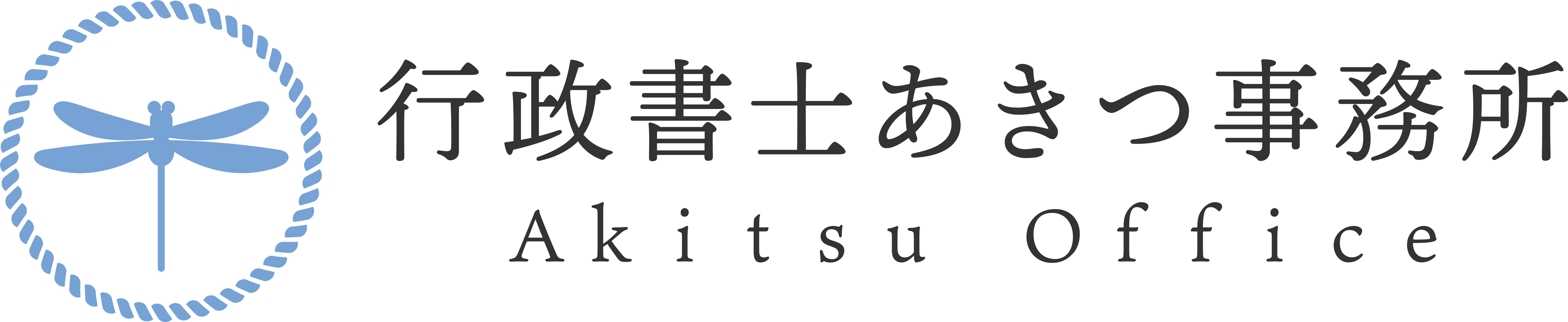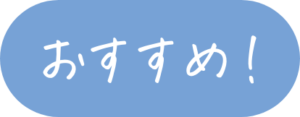遺言書を作成しておいた方が良い人10選を解説!

遺言書を作成すべきケースとは
相続手続きや遺言書に関するご相談をする中で、遺言書がないために、解決するまで1年以上、手続き費用も多額に掛かってしまうなど、残された相続人にとって負担は想像以上のものです。
それでは、一体どういうケースの方が、遺言書を書いておくべきなのか、遺言書を作成していない場合どういうことが想定されるのかを解説していきます!
1 遺産の分配方法を、生前自分で決めておきたい場合
相続発生後、亡くなった方の相続人には、民法で定められた法定相続分に応じた相続権が生じています。
しかし、その法定相続分ではなく、「誰に、何を、どのくらい相続させる」という遺産の種類・量、その遺産を渡す
相手を、生前のうちに指定しておきたい場合、遺言書の作成が必要です。
例えば、「長男に土地・建物、長女に銀行預金すべて」または、「すべての財産を長男に相続させる。」などです。
これを「特定財産承継遺言」と言い、相続発生後、相続人は、単独で銀行預金解約手続きや不動産の名義変更登記手続きなどの遺産承継手続きを行うことが出来ます。
遺言書を作成していない場合は、原則、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
ですから①法定相続分どおりに全員が相続する方法、または②法定相続人の皆さんで遺産分割協議を行い、全員で決めた分割内容どおりに相続する方法の二つが考えられます。
また自筆証書遺言は、時間を要する検認手続き、相続人全員への通知などが必要です。
※遺言書があった場合でも、遺留分の請求を受けた場合は、応じる必要があります。
2 相続人が多数いる
相続人が多数になることが想定されていれば、生前のうちに、遺言書を作成し財産を渡す人を決めておくことで、遺産分割協議はせず、遺言書の内容とおりに遺産を引き継ぐことが出来ます。
特に亡くなられた方がご高齢の場合などには、法定相続人が10~20人以上ということは良くあることです。
亡くなられた方の過去の婚姻時の子や養子縁組などが関係すればさらに複雑です。
このケースで遺言書がない場合、相続人全員の合意が必要となりますが、
一部の相続人と連絡が取れない、また一切話し合いに参加してくれない、遺産分割協議が出来ないことなどはよくあることです。各相続人に対し連絡をとる際も丁寧な対応が必要です。
協議がまとまらない場合、最終的には、遺産分割調停や遺産分割の審判など、時間も費用もかなりの負担となることも想定しておく必要があります。
そのためやはり遺言書の作成は非常に効果的です。
3 相続人が誰もいない
相続人が誰もいない場合とは、一般的に、配偶者、親や子、兄弟姉妹など相続人全員が生存していない場合をいいます。
最近は、「おひとり様」、ご夫婦のみの場合「おふたり様」などといわれます。
このような場合、日頃から良くしてくれた親戚、知人、恩人、友人、又は慈善団体への遺産の寄付など、遺言書を作成していれば、自分の財産を誰かに託すことが出来ます。
特に土地や建物がある場合、空き家になる前に、出来ることならどなたかに引き継いでいただくことも考える必要もあるかもしれません。
相続人がいないケースで、かつ遺言書がない場合は、民法の規定により、相続財産清算人選任など家庭裁判所での手続きが必要となり、最終的に相続人がいないことが確定すれば、遺産は国庫に帰属することになります。
つまり、亡くなられたあと、遺産は、国の所有となるのです。
日本経済新聞の記事では最高裁への取材で2023年度は1,015億円が国庫に帰属しており、10年で3倍以上となっており、現在も単身者数は増加傾向です。
自分の遺産は特定の使途や目的に使いたい、とお考えの場合は、早めに遺言書などの相続対策・生前対策をおススメいたします。
4 前婚や未婚相手との間に子がいる
前婚や未婚相手との間に子がいるケースで、現在の婚姻で生まれた子と、前婚で生まれた子が、遺産相続で争うというお話は、みなさん想像できるかと思います。
遺言書を事前に作成していない場合、相続発生後に、相続人全員での遺産分割協議が必要となりますが、その際に疎遠な相続人、特殊な関係性などもあり、お互いの言い分が対立する可能性が想定されます。
このような場合も遺言書があることで、紛争を事前に防ぐことが可能です。
その際は遺言の内容も十分に検討する必要があります。遺言書の作成行為自体が無効。とする相手方からの提訴の可能性もあるからです。
また遺言書の最後に、「 付言 」を書き記すことも有用です。遺言書を用意した理由や最後の感謝の気持ちを遺言書に残すことにより、相続人全員が、遺言者の御遺志を理解し、揉めることなくスムーズな遺産承継手続きとなることもあります。
他の相続人が請求する遺留分については、民法の規定により受け入れる必要があります。
5 他の相続人と揉める可能性がある
相続人同士、これまでの関係性から揉めそう。遺産分割協議の成立が難しい、などの状況であるのであれば、遺言書を作り相続分の指定をしておいた方が良いかもしれません。
例えば、「妻にすべての財産を相続させる」などの内容の遺言書を作成しておくことで、相続発生後の相続手続きをされるご家族の負担を軽くすることが出来ます。
また遺言作成の際は、その内容に、「遺言執行者」を選任されることをおすすめします。
遺産のうち預貯金の解約や不動産の登記手続きも遺言書や遺言執行者が選任されていることで、通常であれば必要となる書類も不要となる場合や他の相続人の協力が不要となる場合もあります。
遺言書がない場合、前述したとおり、相続人全員での遺産分割協議が必要となりますが、中には、話し合い自体ができない、または意見が対立するなどの理由から結論がでず、遺産分割調停や審判などの裁判所手続きも必要となる場合もあります。
6 遺言者が、認知症を発症する可能性がある、またはその不安がある
自分の財産を誰かに渡したいと考えたとき、
①生前に贈与する方法、そして②遺言書で死後に相続させる、又は贈与する方法がありますが、どちらも遺言者ご本人の遺言能力、意思能力が必要です。
ご自身が認知症を発症してしまった場合、遺言書の作成や生前の贈与契約は出来なくなってしまいますから、その場合、死後の遺産相続については、法定相続分どおりに分配、又は、相続人全員の遺産分割協議の上、遺産を分配していくことになります。
ですから、自分の死後、遺産を渡したい方がいる場合には、意思能力があり、意思表示が可能なうちに、(証人2名の協力も必要な)公正証書での遺言書を作成しておくことで、客観的な遺言能力・意思能力については証明できますので、他の相続人からの疑義を持たれる可能性は低く、ほぼ確実に想いどおりに遺産を渡すことが出来ます。
(※ただし、遺留分については請求可能です。)
さらに、よりライフスタイルの流れに合わせるとすれば、
認知症ではない人で、年齢の経過とともに足腰が悪くななってしまった際に、行政手続きや銀行手続きまたは病院・介護施設などの入所退所手続きなど身近なサポートを任せることできる財産管理委任契約
実際に認知症を発症した場合、ご自身の銀行口座や不動産の売買などは、自分自身も、家族も一切できなくなってしまいます。その後、裁判所で成年後見人を選任する手続きが必要になり、成年後見人には、弁護士や司法書士が多く選任され、認知症の方の財産管理を行います。
このようなことを想定して、自分か認知症になった時、自分の希望の人に財産管理を任せたい場合に、任意後見契約があります。
自分の信頼できる人との間で、認知症になった場合に任意後見人になってもらう契約を事前に行います。
その後、実際に認知症の恐れが生じてきた際、裁判所の手続き後に、正式に任意後見人として、認知症の方の預貯金の管理など、財産管理をすることになります。
これらの二つの契約を、遺言書の作成の際に、同時に公正証書として作成しておくことによって、
認知症になっていないけれど足腰が不自由な時、そして、その後認知症になってしまった時、どちらのタイミングでも、事前にお願いをしておいた希望の人がご自身の財産管理を、正式に代理することができます。
7 相続人が一人が認知症である
相続発生後、複数の相続人の一人が高齢で認知症である場合、その方は遺産分割協議で意思表示を行使することができません。そのため、その人の代わりとなる成年後見人を家庭裁判所から選任してもらう必要があります。
(成年後見人は、一般的には、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士など士業が選任されることが多いです。)
そして成年後見人選任後、認知症の方に成り代わり、相続人全員の遺産分割協議に参加することになります。
通常、遺言書を作成していれば、遺産分割協議は必要ありませんので遺言書の内容どおりに遺産承継を行うことが出来ます。
そのため、相続人の一人である認知症の方の意思表示も不要となりますので、成年後見人選任手続きは不要となるのです。
このように遺言書を残しておくだけで、ご家族が負担する相続手続きの費用や時間は、全く異なったものとなるのです。
8 相続人以外の人に財産を残したい場合。
自身の死後、自分のために良くしてくれた人や法定相続人以外の親戚や知人、友人などに財産を渡したい場合、遺言書が必要です。遺言による贈与、「遺贈」といいます。
遺言書がない場合は、法定相続人のみが遺産を承継することが出来ます。
親族については特別の貢献等があった場合には、寄与分や特別寄与料などの制度がありますが、あくまでも法定相続人に対し、申出る、請求する行為が必要ですので関係性などから難しい面もあります。
9 内縁者(事実婚)に財産を残したい場合
最近少しずつ広まりつつある事実婚や内縁関係の相手へ、遺産を残したい場合、遺言書が無ければなりません。
遺言書がない場合、当然のことながら、戸籍上の法定相続人とはなりませんので、内縁(事実婚)の相手に遺産を残すことは出来ません。
このような場合に作成すべき遺言書は、戸籍上の他の法定相続人からの疑義を持たれないように、やはり公正証書遺言の作成を強くお薦めいたします。
また特に遺産の中に土地や建物があり名義変更が必要になる場合、「遺言執行者」を指定しておくことが重要です。遺言執行者は、亡くなった方が死後の遺産承継手続きを任せる人です。
遺言書があったとしても、この遺言執行者が指定されていない場合、不動産の名義を内縁者へ変更する法務局への登記申請の際、他の法定相続人の協力(署名や実印印鑑など)が必要となります。
逆に遺言執行者が指定されていれば、単独で名義変更の登記をすることが可能になります。注意すべきポイントです。
10 慈善団体などに財産を寄付したい場合。
ご自身の死後、その財産の一部または全部を、希望する団体へ寄付したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
これは遺贈寄付といい、近年おひとり様や子や孫など財産を引き継ぐ人がいない方などの増加や少額からの寄付も認知されたことに伴い、広く知られるようになりました。
2024年9月公表の「遺贈寄付白書」によると年間約1000件を超え、寄付額合計年間平均300億~400億。今後も増加傾向のようです。(ちなみに英国は年間4000億~5000億円、アメリカは4兆~5兆円規模のようです。)
また遺贈により寄付された遺産については、不当なものではない等の諸条件はありますが、相続税の対象から除外されることがあります。
遺贈寄付の方法は、特定遺贈や包括遺贈などとも言いますが、特定の不動産など現物を指定し、そのものを遺贈寄付する方法、または遺産全部や何割など割合を決めて寄付する方法、また遺言執行者によってすべて現金化した上で遺贈寄付する方法などがあります。
寄付の内容や方法により、寄付を受けた団体側が負債も引き継ぐことになったり、納税義務が発生する場合などもあるため、寄付先の団体への申し出や打ち合わせをし、弁護士や行政書士などの遺言書作成の専門家とも相談し、遺言書の内容を作成する必要があります。
例えば、配偶者、子や孫がいないなど、相続人がいない方は、死後の財産は国庫へ入ることになります。
希望の団体への財産の寄付について、少し考えてみるのも良いかもしれません。
国連UNHCR協会
日本承継寄付協会

遺言書の作成の注意点
遺言能力とは
遺言をするためには遺言能力が必要です。
遺言能力とは、遺言者が遺言の内容を理解し、その結果を認識できる能力のことです。
遺言は、遺言者が亡くなった後に、その効力が生じます。
そのため、遺言書を作成する時点で、自分の死亡後に、その効果が発生し、どのような結果となるかを理解している必要があります。これを遺言能力といいます。
遺言に関する紛争はこの遺言能力があったのか?なかったのか?をめぐって、遺言無効の裁判が提訴されることもあります。
遺言を作成するにあたっては、可能であれば、他の相続人には事前に話をしておくこと、そして、遺言書は、証人2名、公証人も関与する公正証書遺言を選択することを強くおすすめいたします。
まとめ
相続や遺言は誰のためのもの?
このようにいくつかのケースをご覧いただきましたが、相続人の数、それぞれの関係性や相続人の健康状態、様々なケースにより相続手続きが非常に複雑化する可能性があります。
遺言書を残してくれていれば・・・。
残されたご家族のこのような言葉はよく聞く話です。
遺言書の内容は様々です。
ぜひ相続や遺言のことを知って、将来のご自身のこと、ご家族のことを考えてみると、これまで少し気になっていたことがより身近に感じられるかもしれません。
今からでも生前対策・終活を始めてみませんか?
考えもしなかったいろんな想いや気持ちが感じられるかもしれません。
弊所行政書士あきつ事務所では、相続や遺言を専門業務として、ご相談も随時承っております。
ご質問やご相談がございましたら、ホームページのお問い合わせメールから、またお電話から、インスタグラムのダイレクトメールから、ご連絡お待ちしております。
出張相談可能です。ご自宅などご希望がございましたらご遠慮なくご相談ください。