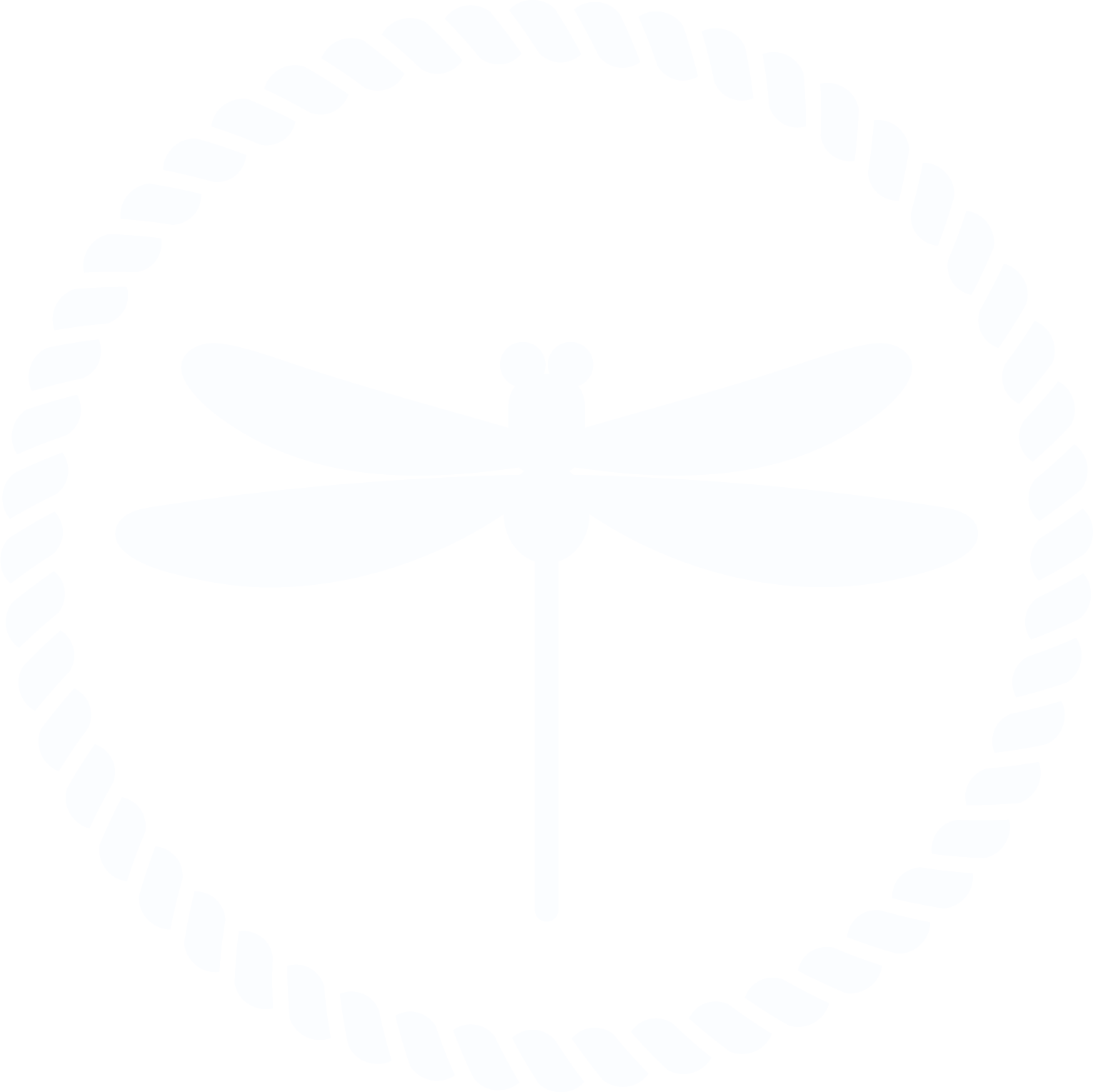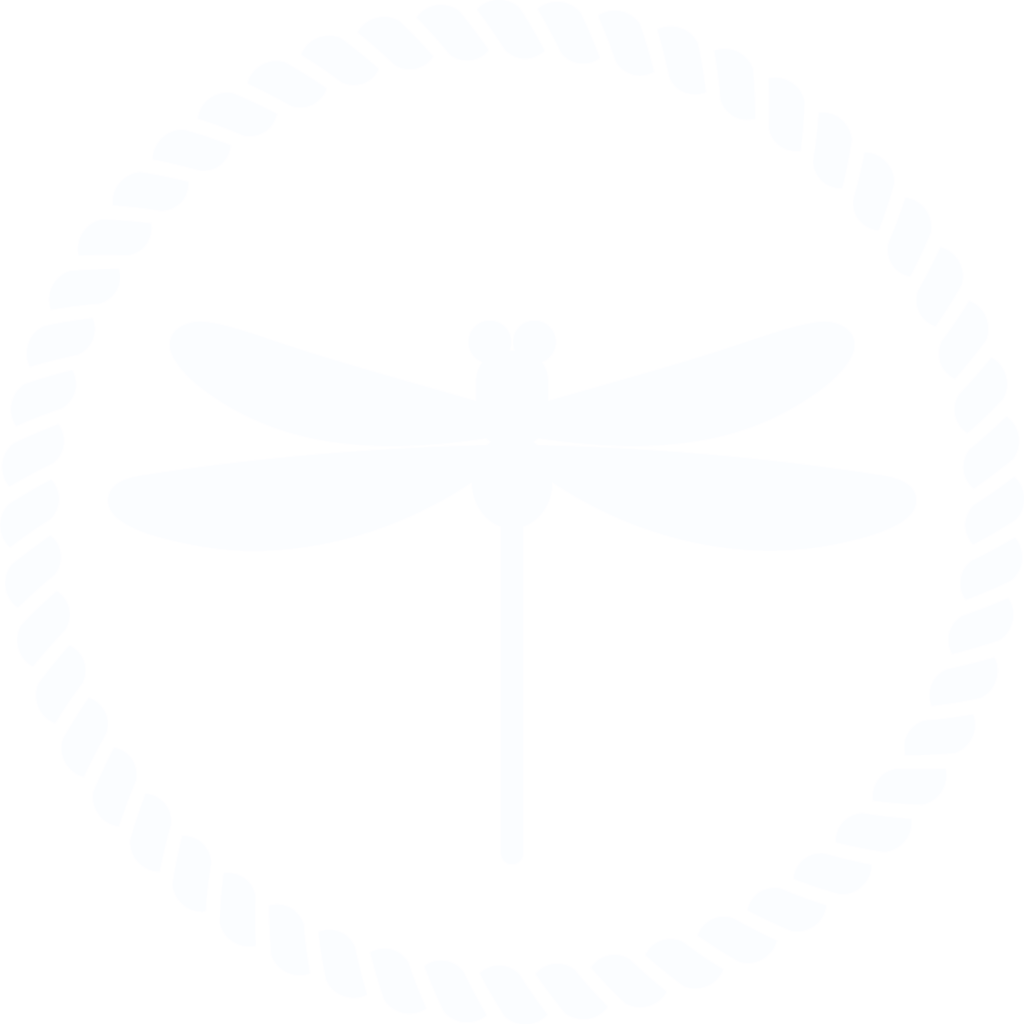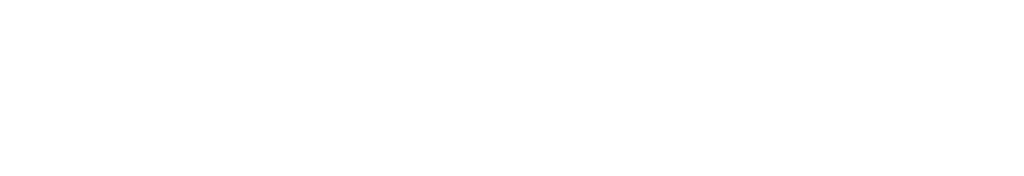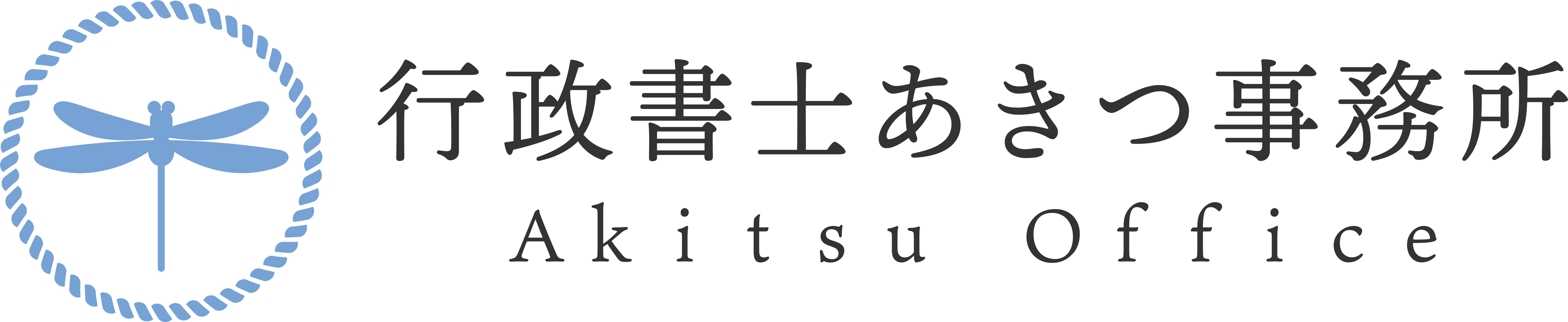遺言書の書き方と遺言書の例

遺言書は、相続に関する重要な文書であり、正しい書き方を理解することが大切です。
具体的な見本や例文を通じて、実際に遺言書を作成する際の参考にしていただければ幸いです。
遺言書の具体的な書き方
■ 簡単な遺言書の書き方と例文
遺言書を書く際は、まず基本的な構成を理解することがとても重要です。
遺言書は、遺言者の意思を明確に伝えるための文書となることから、以下の要素を含む必要があります。
1. 遺言書のタイトル(例:遺言書)
2. 遺言者の氏名、住所、生年月日
3. 相続人の氏名、関係、相続分
4. 財産の詳細(不動産、預貯金、動産など)
5. 日付と署名
具体的な例文としては、「私は、私のすべての財産を妻の花子に相続させる」といった形で記載します。
このように、シンプルで明確な表現が求められます。
■ 自筆・手書きのポイント解説
自筆証書遺言は、遺言者が、自ら手書きで作成する遺言書です。
法律上、遺言者の意思を示すためには、自筆であることが求められます。
以下のポイントに注意して作成しましょう。
・全て自分で手書き記載すること
・日付を明記すること
・訂正部分は二重線で消し、押印すること
・署名を忘れずに行うこと
これらの要件を満たさない場合、遺言書が無効になる可能性がありますので、注意が必要です。
公正証書での遺言の場合は、自筆・手書きでの作成は不要です。
公証役場に遺言書の案文を作成し提出し、「遺言公正証書」として作成、完成します。
■ 全財産の記載方法と注意点
遺言書には、全財産をどのように相続させるかを明確に記載する必要があります。
具体的には、以下の情報を含めることが重要です。
1. 財産の種類(不動産、預貯金、株式など)
2. 財産の所在地や口座番号・証券番号など
3. 相続人の氏名と相続分
例えば、「私の所有する下記記載の不動産を長男の太郎に相続させる」といった具体的に特定する記載が求められます。
また、相続人が複数いる場合は、「長男に100万円、長女に100万円」「長男に預貯金の半分、残りの半分を長女に相続させる。」など各相続人の相続分を明確にすることがトラブルを避けるために非常に重要です。
遺言書作成のための準備
■ 必要な書類とその整理方法
遺言書を作成する前に、作成に必要な書類を、事前に準備し、整理しておくことが大切です。
以下の書類を準備しましょう。
・戸籍謄本(遺言者と相続人のつながりがわかる戸籍一式)
・不動産登記簿謄本(不動産の所有権確認用)
・預貯金通帳のコピー(金融資産の確認用)
・遺贈(遺言による贈与)の場合は、受遺者の住民票
これらの書類を整理することで、遺言書作成時に必要な情報をスムーズに確認できます。
また、書類はファイルにまとめておくと、後の手続きが楽になります。
■ 相続人の明記とその重要性
遺言書には、相続人を明確に記載することが不可欠です。
相続人が誰であるかを明記することで、遺言者の意思が正確に伝わります。
まず戸籍や住民票を取得し、正確な住所、氏名、生年月日を確認することから始める必要があります。
相続人の記載方法は以下の通りです。
・氏名 ・住所 ・生年月日
・関係(例:妻、長男、次女など)
具体的には、「私の有するすべての財産を、妻、〇〇(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる」といった形で記載します。
相続人を特定し明記することで、後のトラブルを避けることができます。
■ 遺言書の保管方法と執行
遺言書を作成した後は、その保管方法が重要です。
遺言書は、遺言者が亡くなった時に効力が発生します。
確実に遺言内容が実行されるように、適切な場所・方法で、保管する必要があります。
以下の保管方法があります。
1. 自宅の安全な場所(例:金庫)
2. 法務局での保管(自筆証書遺言書保管制度)
3. 信頼できる専門家に預ける
4.信頼できる親族に預ける
法務局での保管は、遺言書の存在を公にするため、相続人が見つけやすくなります。
遺言書の記載の中で、信頼できる人を『 遺言執行者 』に指定しておき、遺言書の内容が確実に、正確に、実行されるようにしておくことが大切です。
トラブルを避けるための対策
■ 遺言書が無効になるケース
遺言書が無効になるケースは多岐にわたります。
以下のような場合には、遺言書が法的に無効とされることがあります。
・遺言者が未成年または精神的に不安定な場合
・遺言書が自筆でない場合
・必要な署名や日付が欠けている場合
・遺言能力、意思能力が疑われる場合。
これらの要件を満たさない場合、遺言書は無効となったり、遺言書自体が疑われ紛争になったりします。
その場合、相続人全員が、民法の法定相続分どおりに相続することは可能です。
もしくは、相続人全員で話し合いを行い、遺産の配分を決め、遺産分割協議書を作成します。
その場合は、遺産分割協議書と実印、印鑑証明書が必要。
そのため、遺言書作成時には、法律の要件をしっかりと確認することが重要です。
■ 相続税や負担についての考慮
遺言書を作成する際には、相続税やその他の負担についても考慮する必要があります。
相続税は、遺産の総額に応じて課税されるため、事前に計算しておくことが重要です。
以下のポイントを考慮しましょう。
・相続税の基礎控除額 (3,000万円+600万円×3(法定相続人数))
・相続財産の評価額
・相続人の人数
これらを踏まえた上で、遺言書に記載する内容を検討することで、相続人にかかる負担を軽減することができます。
遺産総額が、相続税の基礎控除額より少ない場合は、相続税は課税されません。
■ 遺族への配慮と付言事項の活用
遺言書には、遺族への配慮を示すための『付言事項』を記載することができます。
付言事項とは、遺言書の本旨とは別に、遺言者の思いを伝えるための文言です。
例えば、「私の財産を受け取った後は、家族仲良く過ごしてほしい」といった内容を記載することができます。
このように、遺族への配慮を示すことで、遺言書の内容がより円滑に執行される可能性が高まります。
遺言書に関するよくある質問
■ 遺言書は誰が作成するべき?
遺言書は、相続を考えるすべての人が作成するべきです。
特に、子供がいないご夫婦、おひとりでお暮しの方、また財産がある方や、お世話になった方に特別な配慮をしたい方、寄付をしたい方などは、遺言書を作成することで、遺産の行方が明確になり、遺族間のトラブルを避けることができます。
また、年齢や健康状態に関わらず、早めに準備をしておくことが推奨されます。
■ 遺言書作成にかかる費用
遺言書作成にかかる費用は、作成方法や専門家に依頼するかどうかによって異なります。
以下のような費用が考えられます。
・自筆証書遺言の場合:基本的に費用はかからないが、書類整理に手間と時間がかかる
・公正証書遺言の場合:公証人手数料が必要(数万円程度)
・専門家に依頼する場合:数万円から十数万円程度
費用を事前に把握しておくことで、計画的に遺言書を作成することができます。
遺言書の記載例やテンプレートの活用
具体的な記載例を参考にすることで、どのように書けばよいかが明確になります。
また、インターネット上には多くのテンプレートや例が公開されているため、自分の状況に合ったものを選ぶことも出来ます。
その例を参考にして、自分の意思をしっかりと反映させることが重要です。
【遺言書の作成例(基本的な文例)】
※作成する際は、必ず全文を自分で手書きしてください。
遺 言 書
※あなたの氏名
遺言者 山田太郎は、次のとおり遺言する。
※「すべての財産を夫や妻に渡したい場合の書き方
1 遺言者は、遺言者が有する全ての財産を、
遺言者の妻、山田花子(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
※財産を何人かに分けて渡したい場合や特定したい場合の書き方
1 遺言者は、遺言者が有する次の財産を、
遺言者の妻、山田花子(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
(1) 土地 : 福岡県福岡市 ○○番○
(2) 建物 : 福岡県福岡市 ○○番地○ 家屋番号 ○○番○
(3) 遺言者名義の預貯金 福岡銀行〇〇支店 口座番号 1234567 山田太郎
2 遺言者は、遺言者名義の株式会社××の株式1万株を、
遺言者の長女、山田法子(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
3 遺言者は、前記1、2に記載した財産以外に、遺言者の有する財産があった場合、
そのすべてを妻の山田花子に相続させる。
※遺言執行者を指定する場合の書き方の例です。(遺産引継ぎの事務手続きをおこなう人です)
4 遺言者は、妻、山田花子を遺言執行者に指定する。
遺言執行者は、必要と認めたときは、その任務を、第三者に行わせることができるものとする。
※付言事項がある場合の書き方の例です。
(付言事項)
妻の花子には、最後までいろいろと苦労をかけました。
長年にわたり連れ添ってくれて感謝しています。
法子もお父さんの大事な娘です。お母さん共々、身体に気をつけて幸せに暮らしてください。
令和○年○月○日
※この遺言書を書いた日付
住 所 福岡県福岡市 ○○番○ ※あなたの住所
氏 名 山 田 太 郎 ㊞ ※あなたの氏名 ※実印で押印
生年月日 昭和○○年○○月○日生 ※あなたの生年月日