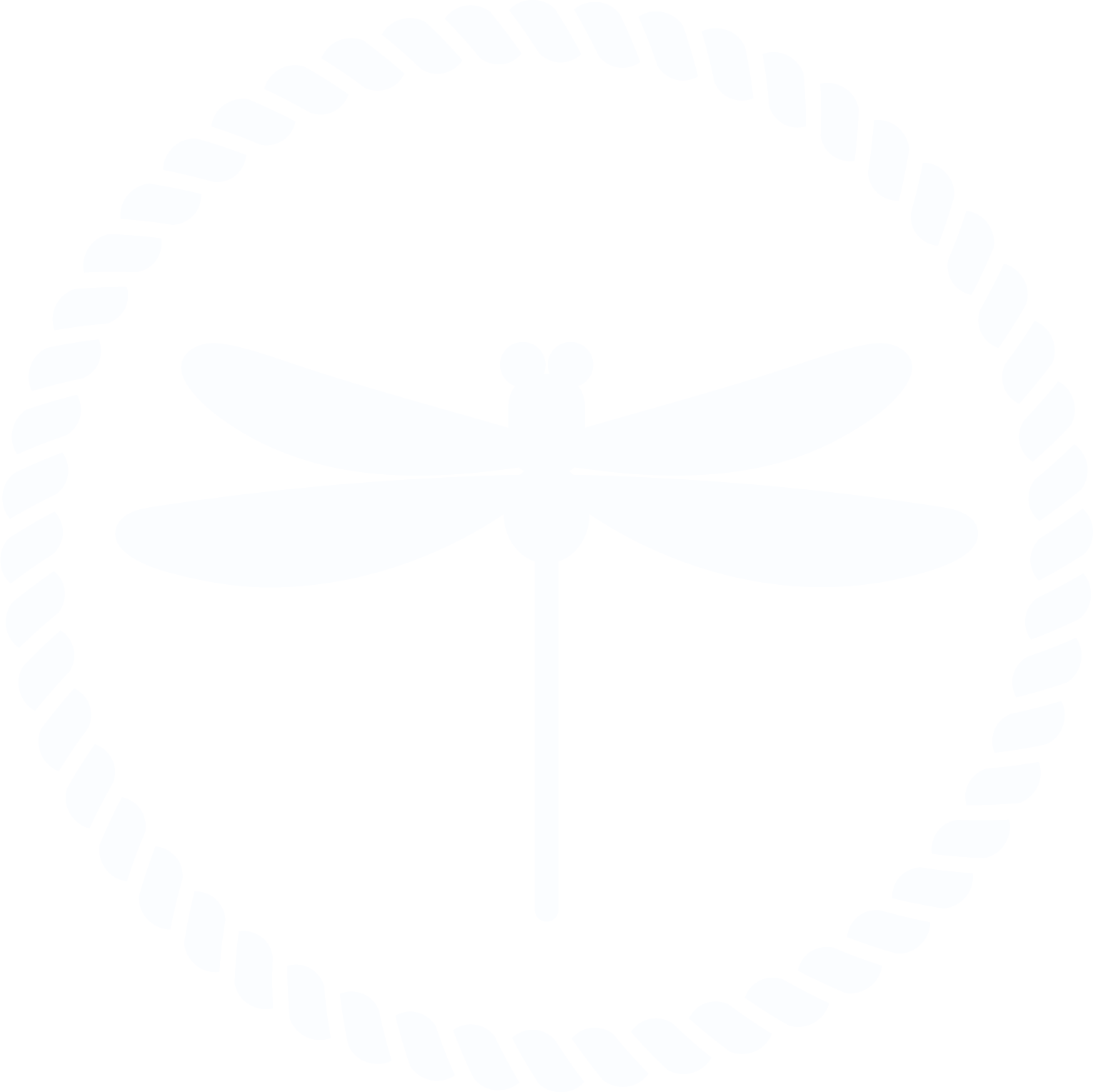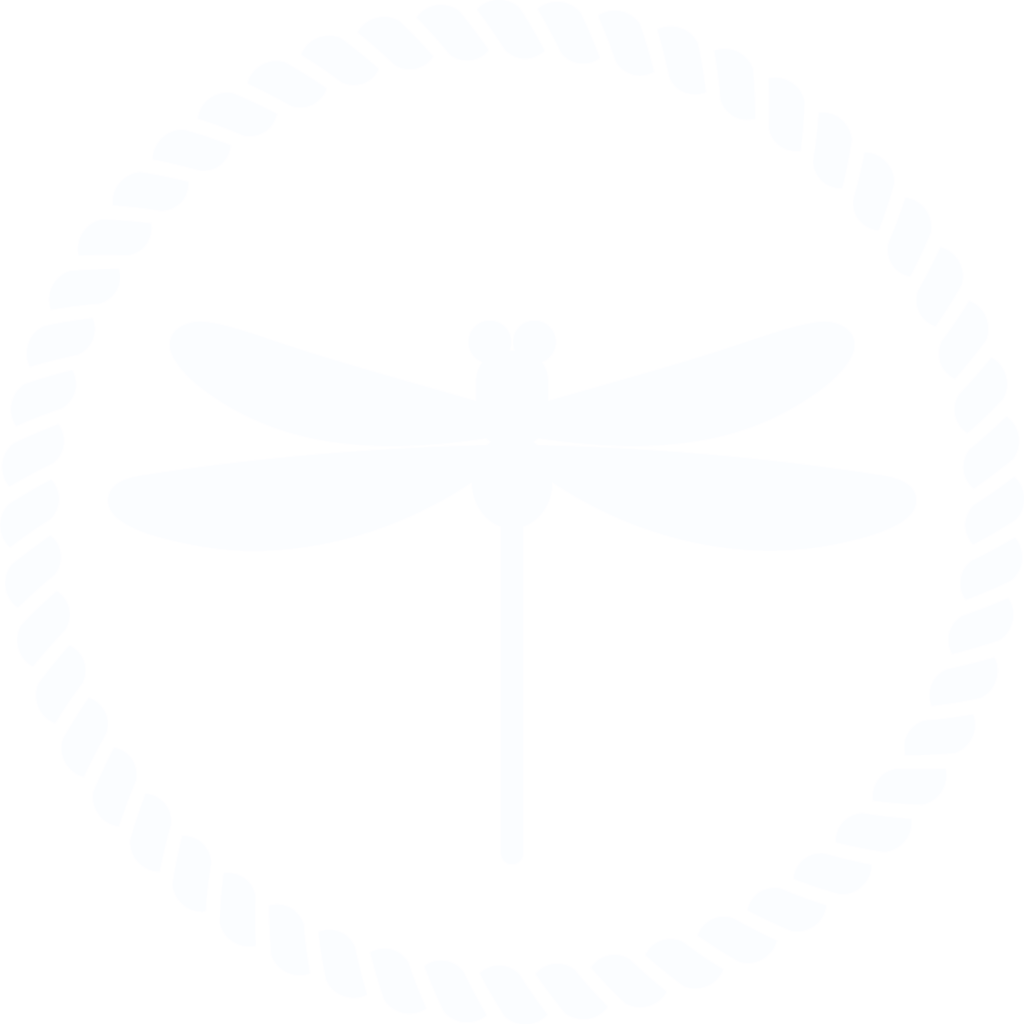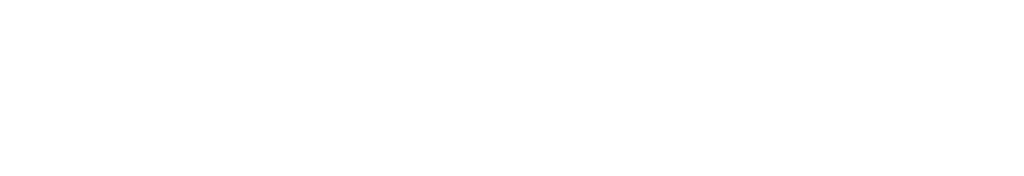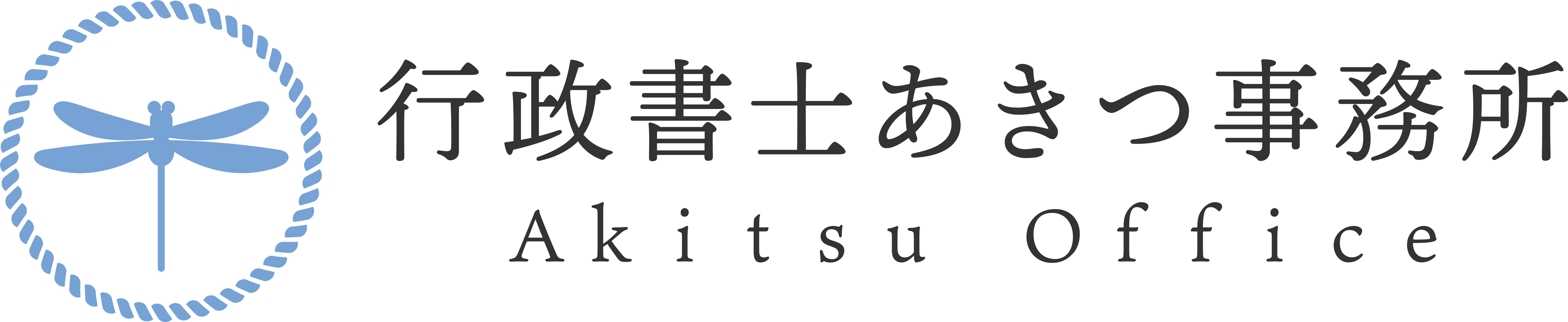初心者でもわかる遺言書作成の基本を解説

初心者でもわかる遺言書作成の基本
遺言書の重要性と役割
現在日本の65歳以上の人口は約3623万人、総人口に占める割合(高齢化率)も29.1%となっています。
そしてその高齢者の方々がお亡くなりになった後、そのご家族が「相続」に関わることになります。
それほど関心なく生活しているあなたも突然その当事者となる可能性があります。
考えられるケースは、
・子供や既に親がいないご夫婦の夫が亡くなった場合。(夫ではなく妻が亡くなった場合も同じ)
相続人は、妻(又は夫)だけではありません。亡くなった夫(妻)の兄弟姉妹も相続人となります。
そのため、遺言書を作成しておくことで、妻(夫)にすべての財産を残すことが出来ます。
(兄弟姉妹には、遺留分を請求することはできません)
・家族以外で特にお世話になった人などに財産を残してあげたい時、遺言書が必須です。
これを遺言による贈与、「遺贈」と言います。
相続人、親族同士これまで仲が良かったとしても、日頃からお互いをよく知っていて、意思疎通、情報のやり取りが出来ている人は、実はあまりいないのです。
相続財産の分け方について、「他の相続人も承諾するはず」または、「あの時言ったじゃないか」「そんなこと一言も聞いていない」など、お互いの立場や利益・不利益が違うため、その時になってみなければ、相手の考えや言い分はわかりません。巨額の遺産ではなくても、遺産相続争いは現実に多く発生しています。
事前に遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後、このような無益な遺産相続の争いを未然に防ぐことができます。
遺言書を遺しておくことは、残されたご家族への想いやりそのものなのです。
相続における遺言書の効力
遺言書は、遺言者の死亡の時から、効力が生じます。(民法985条)
遺言書の内容にできること
・遺産の分割方法を指定することが出来ます。
すべての財産を妻へ、預貯金は長男へ、不動産は長女へ、など
・法定相続人以外の人へ、遺産を渡すことが出来ます。
・遺産を希望の団体などへ寄付することが出来ます。
・婚姻関係のない人との間の子を、遺言書の中で認知することが出来ます。
・遺言書の中で、相続人から廃除したり、廃除を取り消したりできます。
・遺言執行者を遺言書の中で指定しておくことが出来ます。
遺言執行者とは、遺産承継の手続き一切を取り仕切ります。他の相続人は勝手に遺産を処分できませんので、相続人が公平に遺産承継を受け入れる必要があります。(親族のどなたかまたは行政書士等専門家がなることが多いです。)
遺言書があったとしても、遺留分については請求が可能です。
遺言書の種類とその特徴
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言は、遺言書そのものを自分で書き作成する方式の遺言です。
自筆証書遺言の最大のメリットは、費用がかからず、自宅で手軽に作成し保管できることです。
また遺言作成に際しては、民法のルールがあります。
基本的には、遺言者が全文、日付、氏名を自書しなければなりません。
また財産目録の作成については、自書する必要はなく、パソコン等で作成することが出来ます。ただし、その作成した目録用紙の一枚一枚に署名・押印をすることが必要です。
また確実に遺言内容を実現するために、自分の死後、遺言の存在が明らかになるよう信頼できる人や遺言執行者などに知らせておくことが大切です。
また自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」手続きが原則必要となります。
※現在、法務局で、「遺言書の保管制度」が開始しておりますので利用するのもひとつの方法です。(預けた場合検認は不要となります。)
※自筆証書遺言のデメリット
第三者が関与せず、一人で作成が可能なため、認知症など、作成時の遺言能力・意思能力等に疑義がある場合、または第三者の関与により筆跡を疑われるなど、作成過程に問題があると考えられてしまい、遺言無効訴訟や他の相続人からの遺留分侵害額請求等の裁判手続きを執られてしまう場合もケースによりあります。
最終的な意思である遺言の内容が実現できなければ、遺言を作成した意味が無くなってしまいます。
自筆証書遺言の作成は、手軽な一方、非常に注意も必要です。
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言とは、遺言書を公証役場にて、本人・公証人・証人2名が一緒に確認し遺言を作成する方法です。
利害関係のない公証人や証人が作成に関与しますので、遺言者の遺言をする意思能力は明らかです。
遺言書の原案自体は、よく考えて作成する必要がありますが、その原案を、公証人が正式な書面である公正証書として作成します。(最後に署名押印が必要です。)体の不自由な方も利用することが出来ます。
公正証書遺言作成後は、公証役場で、書面やデータとして保存されます。
偽造や紛失、災害などの心配がなく、また時間を要する家庭裁判所での「検認」手続きが不要であるため、相続発生後、遺言書を使用して、銀行や不動産などスムーズに遺産承継手続きを開始することが出来ます。
遺言書の中で、遺言執行者を指定していれば、その方(親族や行政書士など)が遺産承継すべてを行います。
デメリットとしては、原案の作成から必要書類の収集、そして公証役場での完成日まで、何度もやり取りがあり、一か月ほど時間がかかること、また作成支援の行政書士や証人の費用、公証人の作成費用がかかることが挙げられます。
(合計でおおよそ15万~20万円ほど)
しかしながら、丁寧に作成しているからこそ、相続発生後、時間のかかる家庭裁判所での検認手続きは不要となりますし、紛失や偽造の心配なくほぼ確実に、遺言の内容どおりの遺産承継手続きを、迅速に、行うことが出来ます。
遺言書を作成することが目的ではなく、確実に希望どおりの遺産承継を実現することが目的です。
遺言書は、死後にご家族への想いを伝える手段でもあるのです。
公正証書遺言を作成していれば、将来については安心されて良いかと思います。
秘密証書遺言のメリットとデメリット
秘密証書遺言とは、遺言の内容は誰にも知られずに、公証役場にて、本人・公証人・証人2名が立ち合い作成する方法です。
公証人や証人2名も遺言の内容を確認することはありません。
遺言者は、自筆またはパソコン等で遺言書を作成し、自筆で署名押印をします。
公証役場にて、この遺言書の入った封筒に公証人、証人2名が署名押印をすることで、遺言をしたこと証明し、記録もしますが、公証役場での遺言書自体の保存保管は行われません。
そのため遺言の内容を確実に執行するためには、紛失・破棄などに注意し、さらに自分が死亡したことを知ることができる信頼のおける人や事前に選んでおいた遺言執行者などへ遺言書を預けたり、またはその保管場所を知らせておく必要があります。
相続人が、秘密証書遺言の存在すら気付かない可能性があります。
実際にはあまり利用されていない方法です。
公正証書遺言の作成の流れ
公証役場での手続きと必要な書類
確認の事項
※ 認知症など遺言能力に問題ないか
※ 視力・聴力は問題ないか
※ 遺言者が公証役場で、自分で署名押印できるかどうか(出来ない場合は、公証人が出張することもできる)
①遺言の原案作成
どの財産を、誰に、どのくらい渡したいのか、また家族への希望など、遺言書に記載しておきたいことを、十分に考え、遺言書の原案を作成することから始めます。
・戸籍類を取り寄せ相続図を作成し、自身が死亡した後の法律上の相続人を確認しておく。
自分が養子の場合、離婚歴がある場合、配偶者と子供がいないおひとり様などケースによっては、当初想定していた人数よりも相続人が増える場合がある。
・財産目録など財産の一覧表を作成し、遺言者自身も、家族も、財産全体が確認できるようにしておく。
②必要書類を収集する
・遺言者本人の戸籍、運転免許書、印鑑証明書、実印
・遺言者の年齢や遺言能力などの状態によっては、医師の診断書
・遺言者と受遺者との関係性がわかる戸籍(相続人が財産を受け取る場合)
・受贈者の住民票(相続人以外が財産を受け取る場合)
・財産の確認できる資料(通帳写し、株現在額、不動産登記事項証明書など)
・証人予定者の氏名・住所・生年月日及び職業、(遺言日当日に印鑑が必要)
③公証役場に連絡を取り、遺言資料を持参または郵送、メールなどで送付する
その後何度か質問や修正のやり取りを行う。
④公証役場から公正証書遺言の最終原案と公証人の費用が提示される。
原案について、修正点や加筆したいことがあれば伝える。
⑤公証役場での公正証書作成日時を予約する。
遺言者ご本人、公証人、証人2名の都合の良い日時に設定する。
⑥遺言書作成当日
当日遺言者、証人が公証役場を訪問し、公証人の進行により遺言書作成手続きを行う。
立ち会うことができるのは、公証人、証人2名、遺言者のみであり、遺言者の家族の付き添いはできない。
遺言者自身の本心が、家族が付き添うことによって左右されてしまう可能性を無くすため。
①公証人が、遺言者に遺言の内容について質問をする。
②遺言者が質問に答える。(遺言書の原案を見ながら答えることはできない。)
③問題がなければ、遺言者、証人2名、公証人が、遺言書に署名押印をし、遺言書完成。
④公証人へ費用の支払い後、公正証書遺言の正本と謄本を、受け取り遺言作成すべてが終了となります。
公証役場での作成手続きにかかる所要時間は、公証役場到着から20分~30分程度です。
行政書士に依頼するメリット
前述した公正証書遺言作成について、行政書士に依頼した場合、以下の手続きを代わりに行うことができます。
・相続関係説明図の作成(市役所などで戸籍住民票などの収集作業)
・財産目録の作成(金融機関での残高証明書や法務局での不動産登記事項証明書収集)
・公証役場との打ち合わせ(財産資料のメール送信や書類の郵送・持参など)
・公正証書作成日の予約の手配(公証人、証人2名、遺言者の都合を確認し日時を調整します。)
・証人2名の手配(当事務所にご依頼の場合、証人2名手配いたします。)
遺言者ご本人にご協力いただくことは以下の2点です。
①遺言の内容について、ご依頼いただいた行政書士の質問にお答えいただくこと。
・財産の確認(銀行、不動産など)や、誰にどの財産を渡したいかなど
・委任状等にご署名いただきます。
②遺言書作成日当日、公証役場に訪問し、公証人の質問にお答えいただくこと。
③完成した遺言書に署名押印していただくこと。
(公証人の質問がどのようなものか、答え方など、すべて事前にサポートいたします。)
検認制度について
「検認」とは、相続人全員に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
このように、検認は、証拠保全の手続きであることから、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
民法では、以下のように定められています。
遺言書の保管者又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。民法第1004条
封印のある遺言書の場合は家庭裁判所で相続人立ち合いの上、開封しなければならない。違反した場合、5万円以下の過料に処せられる。民法第1005条
※ただし、公正証書遺言や法務局の遺言書保管制度を利用している場合は検認手続き不要です。
検認手続きの流れ
①遺言者の死亡後、相続人が申立人となり、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申立てをおこなう。
②家庭裁判所から、すべての相続人に検認期日の通知が郵送される。
③検認期日、申立人・相続人立ち合いのもと、家庭裁判所で遺言書が開封される。
(相続人は各自の判断で検認手続きへの出席or欠席を判断する。)
④家庭裁判所では遺言書の形状、封の有無、加除訂正の状態、日付、署名、印などを確認し「検認調書」にまとめ記録し、検認手続き終了。
⑤申立人等は同時に「検認済証明書」発行の申請をし、受領する。
今後金融機関や法務局など手続きの際、検認の証として必要となります。
これらの検認手続きは、遺言者の死亡後、戸籍の収集、相続関係図作成、財産目録作成の上で行うことが理想的です。
遺産がどのくらいあるのかを把握しておくことが非常に大切です。
検認手続きに必要な戸籍の収集は、被相続人(遺言者)死亡後、様々な事務手続きの最中に、平行して行う必要があり、おおよそ早くて1か月ほどはかかり、戸籍請求先の本籍地が遠方であれば、郵送での取り寄せの為、より時間がかかることになります。
必要書類を揃え、家庭裁判所に「検認」の申立て後、相続人への期日の通知など、裁判所内の事務手続きがあり、実際の検認期日当日までに1か月以上、相続開始から最低2か月ほどはかかることを想定しておいた方がよいでしょう。
さらに検認後、参加した他の相続人から、遺言書を実際に見たあとに、筆跡鑑定の要求等、遺言書自体に疑義をもたれることもあります。遺留分についての主張も想定されることです。そもそも遺言の存在を知らされていなかった人などはその傾向があります。
その点、公証人、証人2名が関与し厳格な手続きで作成する公正証書遺言であれば、検認も不要となり、他の相続人の疑義は少なくなるのかもしれません。
まとめ:遺言書作成のメリットと重要性
遺言書作成を通じて得られる安心感
遺言書を作成する最大のメリットは、安心感が得られることです。
遺言者ご自身にとって不安が無くなり安心感が得られれば、残りの人生をより豊かにすることが出来ます。
また、ご家族にとっても、無益な遺産争いなどを避けることが出来、安心感を得ることが出来ます。
家族への想いを形にする方法
- 最後の想いを、遺言書に残したい。
- 遺言書の内容通りに財産を分けてほしい。
遺言書は、ご自身が亡くなった後に、自分の代わりに想いを家族に伝えるお手紙です。
これまで遺言書がないために、紛争状態になったケースは非常に多いです。また、一度揉めてしまうと話が全く進まなくなってしまいます。遺産分割調停や裁判など精神的にも疲れはててしまいます。
やはり実行性が高く、かつ迅速に遺言内容を実現することが出来る公正証書遺言の作成をおススメいたします。
行政書士あきつ事務所では、遺言書に関する様々なお手続きをサポートしております。
ご不安なことがあれば、どんなことでもお聞かせください。
お時間の許す限り、ゆっくりお話をお伺いいたします。