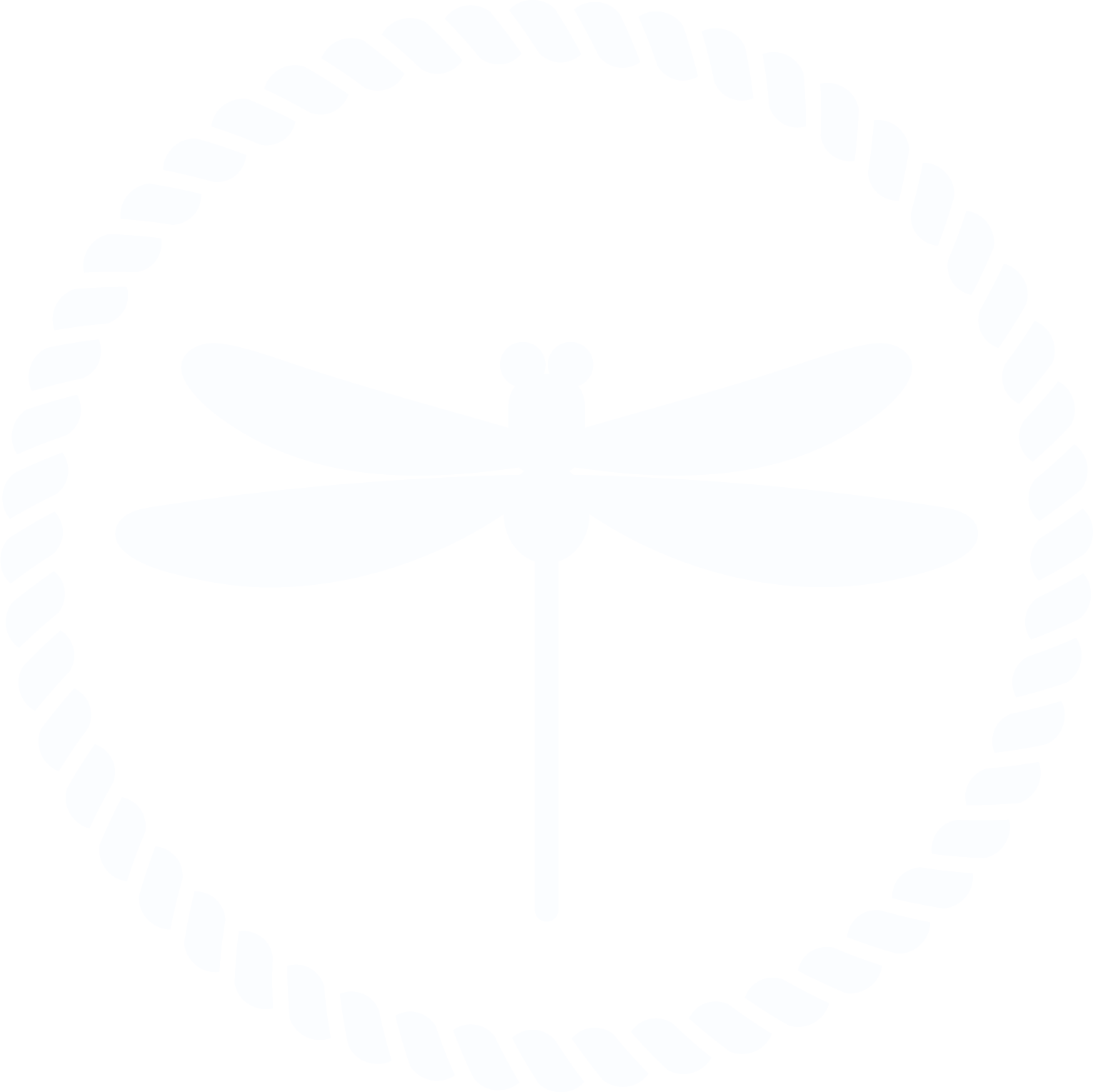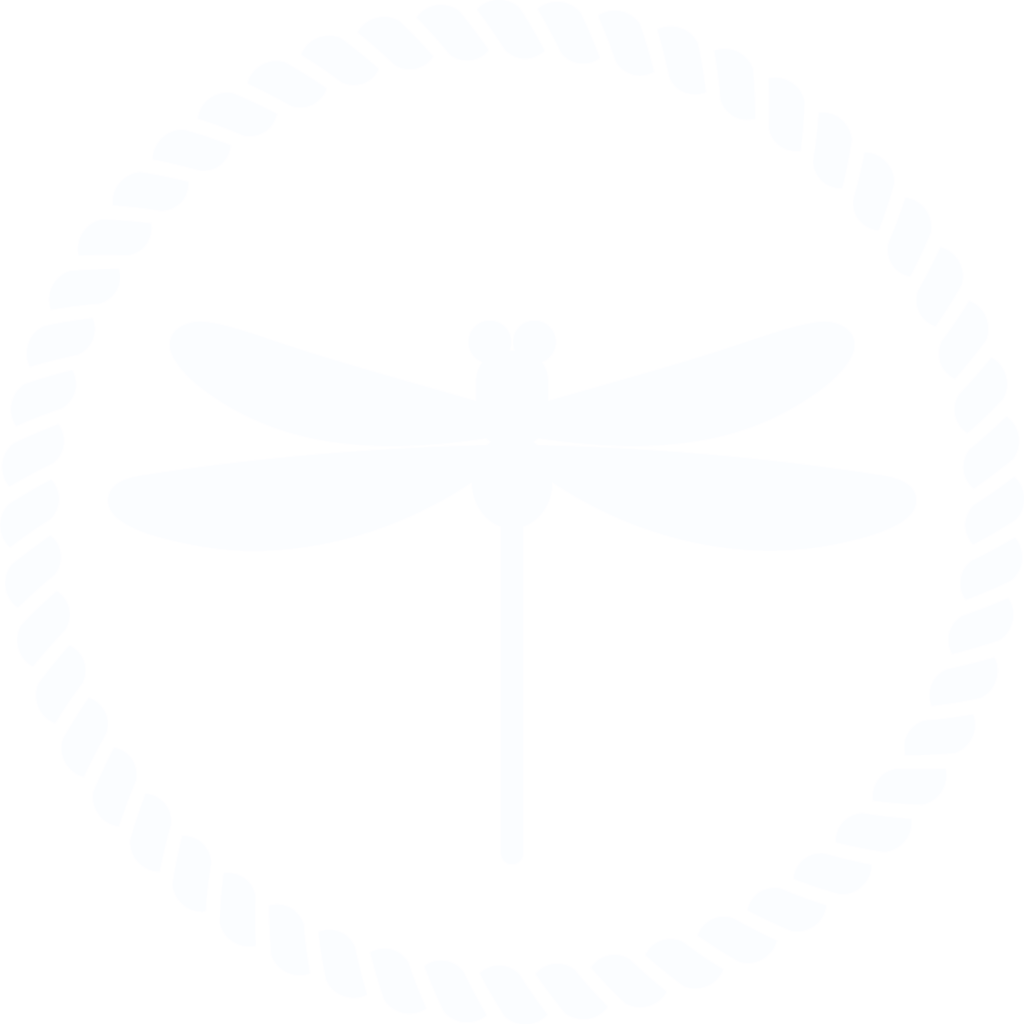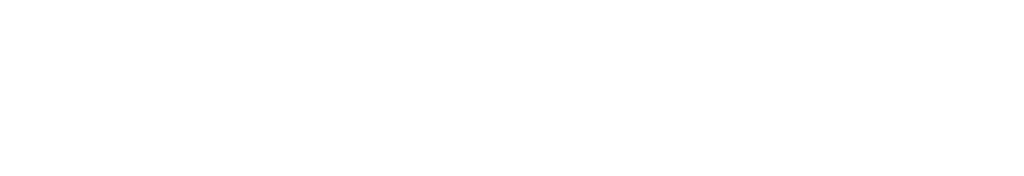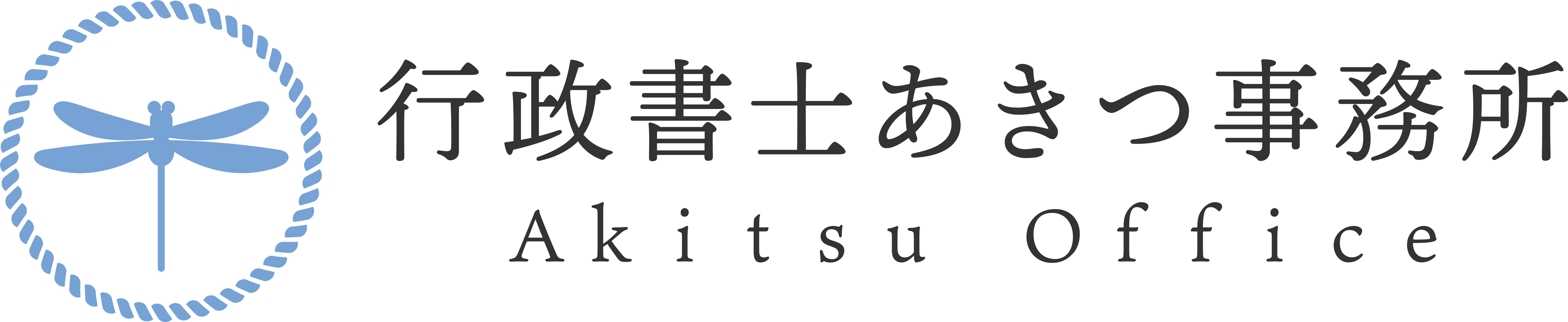事実婚・内縁の妻、内縁の夫に遺す遺言書の作成方法とは?

事実婚・内縁の妻、内縁の夫:相続・遺言書の重要性
遺言書は、亡くなった方の意思を明確に示す重要な文書です。
特に事実婚の関係や内縁の妻や内縁の夫に対して財産を残す場合、
遺言書がなければ他の法定相続人に財産が分配されてしまうため、事実婚や内縁の相手は一切の財産を受け取ることが出来ないことになります。
事実婚や内縁関係は、判例や先例などで、少しずつ理解され法改正なども行われていますが、法律上の婚姻関係ではないため、原則的には民法上の相続権が認められません。
事実婚や内縁関係について、最新の相続法の改正などをチェックすることが重要です。
長く一緒に暮らしているパートナーに遺産を残すため、お互いでよく話し合い、互いに遺言書を作成することで、遺産の承継について、法律上の夫婦に近い状態にすることが出来ます。
遺言書とは何か?基本の理解
遺言書にはいくつかの種類があり、手書きの自筆証書遺言や公証役場で公証人に証明してもらう公正証書遺言などがあります。
遺言書を作成することは、その後の遺族間のトラブルを避けることができ、特に事実婚や内縁の妻や内縁の夫に対しても、法律上の権限を以て、明確に財産を残すことが可能になります。
紛失や改ざんの防止、本人の遺言作成の意思も明確に確認が出来ますので、出来る限り公証役場で証明してもらう公正証書遺言の形式で作成することをおススメいたします。
一か月以上を要する裁判所検認手続きも不要となることも大きなメリットです。
事実婚・内縁関係の現状と法的な取り扱い
①『 事実婚 』とは、法律上の婚姻関係を結んでいないが、実質的に夫婦として生活している関係を指します。夫婦別姓や婚姻することでの仕事のキャリアがなくなってしまうことに対し、お互いでよく話し合い、理解し合意している場合に、「事実婚」という形を自ら積極的に選択しているケースが多いかと思います。
②『 内縁関係 』とは、一般的には、婚姻を望んでおり、夫婦に近い関係性ではあるが、諸事情から婚姻できない、又は婚姻していない状態、が継続している場合に、内縁関係とすることが比較的多いように思われます。
それぞれの関係性のケースは非常に多く、相続権に関する判例は複数あるものの、法的な取り扱いは未だに曖昧であることから、相続分が認められるためには、裁判手続きが必要となることがほとんどです。
このように事実婚や内縁関係である場合、お互いが相手の遺産を受け取るためには、遺言書を作成することが不可欠なのが現状です。
事実婚、内縁の妻や内縁の夫向けの遺言書の書き方
事実婚・内縁の妻や内縁の夫に遺産を遺すためのポイント
事実婚・内縁関係は、法律上の関係性ではないことから、少しでも明確な内容の遺言を残すことが必要となります。
もっとも、遺言書は、遺言者の死亡後に、遺言内容が実現出来なくては意味がありません。
特に死後、他の相続人から遺言書の作成自体そのものに疑義をもたれ裁判となるケースもあります。
そのため、自分で自書して作成しなければならない自筆証書遺言ではなく、公証役場で行う公正証書での遺言書作成を強くおススメいたします。
一般的な遺言書の文例と遺留分
「遺言者は、遺言者の有するすべての財産を、内縁の妻である〇〇(生年月日)に包括して遺贈する。」
法律上の相続人ではないため、遺言による贈与である「遺贈」という形式になります。
(補足:法定相続人へ財産を残す場合は「相続させる」となります。)
ただし、他の法定相続人には法律上守られた「 遺留分 」という権利があります。
例えば、亡くなったパートナーに子がいる場合、通常、一人っ子の相続分は2分の1となっていますが、そのまた半分である「4分の1」が遺留分割合になります。すなわち、すべての財産を内縁の妻に渡す内容の遺言書を作成しても、全ての財産のうち4分の1は、子が法律上請求することができます。
このようなことを理解したうえで遺言の内容を考え、又は事前に話せる人には遺言を残すことについて相談をしておくことも大切です。
遺言執行者の指定の重要性
「遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。」
住所 〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇
遺言書の財産の中に不動産がある場合、一般的には、自分で、又は司法書士に依頼し、不動産の名義を内縁の妻へ変更する法務局への登記申請手続きが必要になります。
この時、内縁の妻と亡くなった方の法定相続人との共同申請が必要となります。
要するに、亡くなった方の実子や両親、もしくは兄弟姉妹などの法定相続人の署名・印鑑登録証明書を提出してもらうようにお願いしなければなりません。
もしかしたら、その中には全く協力してくれない人がいるかもしれませんし、または認知症の方がいらっしゃったり、行方不明の方がいることも想定されます。
このような場合に、「遺言執行者」が選任されていれば、遺言の実現のためのすべての権限を有しますので、他の相続人は関与せず、代わりに遺言執行者が関与することで不動産の名義変更手続きをすることが可能になります。
遺言執行者の指定は非常に重要です。
なお専門家に依頼した場合、遺言執行手続きには当然ながら費用がかかります。
例としては、遺産の1%~(最低30万円~)など、それぞれの専門家により報酬は異なりますので確認が必要です。
遺言の最後に、「付言」のススメ
パートナーへ、又はその他の相続人やご家族に対し、遺言書を残した理由やパートナーへの想い、ご家族への想い、葬儀の希望などを書き記すことが出来ます。
『 付言 』には法的な効果はありませんが、パートナーや他の相続人は、遺言者の考えや最後の想いを知ることが出来、他の相続人の、事実婚や内縁関係についての理解を助け、残された内縁の妻などのパートナーが、相続争いに巻き込まれることを防ぐことが出来ます。
相続税と内縁の法的枠組み
相続税の申告や納税について事前の確認する
事実婚や内縁関係のパートナーが遺言書によって遺産を受け取った場合、相続税の申告や納税が必要となる場合があります。
亡くなった方の財産が、基礎控除額を超えている場合に、その超えた金額に対して相続税の計算をし、申告・納税が必要となります。これは事実婚であっても、法定相続人であっても一緒です。
申告納付期限は、死亡の事実を知った日の翌日から起算して10か月です。
ご家族の構成、相続人の数により基礎控除額は異なりますが、基礎控除最低額3,000万円以上の遺産がある場合は、事前に税務署や税理士へ相続税の相談をしておき、申告・納税が必要になりそうかどうか、またはそのおおよその納税額を知っておくことが重要です。
前もって理解しておくことで、生前贈与や生命保険など、活用できる方法を使い、事前に相続税対策をすることも出来ます。
また事実婚・内縁の妻などの場合、相続税の計算では、通常より多い2割加算の制度が適用されることも想定されます。税務署や税理士事務所などに相談することとおススメいたします。
国税庁:相続税額の2割加算
生前贈与の活用法とその注意点
生前贈与は、亡くなる前に財産を贈与する方法です。
事実婚・内縁の妻や内縁の夫に対して生前贈与を行うことで、相続税の負担を軽減することができます。これにより亡くなったあとに起こる親族との争いを一定程度避けるこができます。
ただし、生前贈与には贈与税がかかるため、計画的に行うことが重要です。
また、不動産や財産の贈与の際には、贈与契約書などを作成し、後々その事実を説明や証明することが出来るように明細や記録を残し、準備しておくことをおススメいたします。
事実婚や内縁関係を文書で明確にしておく
事実婚や内縁関係の方々にとって、日々の生活を送る上で、そして、仕事上で、又は病気になった時、死亡した時、相続問題、それぞれの場面で法律上の夫婦ではないことで思わぬデメリットを受けることも事実です。
出来る限りそうならないように、話し合いをし対策を講じることが、これからも一緒に生きていく上で、お互いにとってとても大切ですし、関係性が深くなり安心感を得ることにもつながります。
以下のような方法例を検討されると良いかと思います。
住民票上の記載を変更する
①住民票を世帯同一にする
②住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と記載することで、婚姻の意思をもって夫婦同然の共同生活を送っていることを公的に示すことが出来ます。
事実婚契約書・事実婚合意書を公正証書として作成しておく
①社会的に信頼性のある公正証書で、事実婚であること、その他合意したこと、遵守すべきことなどを定めた『 事実婚契約公正証書 』を作成することで、行政機関・金融機関・医療機関などの第三者に対し事実婚の関係であることを証明することが出来ます。
②医療機関では、通常、輸血や手術など医療行為への同意は親族のみとなっています。
事実婚契約書や医療同意に関する公正証書を事前に作成しておくことで、医療機関に搬送された際、事実婚であることを証明できます。
またこれにより医療行為や手術の同意書などへの同意についても可能となる場合もあります。
医療機関により考え方もありますので、確認が必要ですが、何も作成していなければ、通常は、親族への連絡を求められる可能性も考えられます。
財産管理委任契約を公正証書で作成しておく(身体不自由対策)
これは認知症を発症していないときに活躍する制度です。
足腰が弱く、不自由になり、自由に外出できなくなってしまった際に、
医療機関への受診、お薬受け取り、施設への入所退所手続き、金融機関の手続き、その他多くの事務を、事実婚や内縁のパートナーに委任しておくことで、正式な代理人として任せることが出来ます。
公正証書で作成することで各機関への信頼性も高くなります。
任意後見契約を作成しておく(公正証書)認知症対策
認知症を発症してしまうと、通帳への入金出金、不動産の管理などの財産管理は、妻や子であってもその権限がありません。「成年後見人」という代理人が財産管理を行うことになっています。
そのため裁判所に親族が選任の申立てをし、「成年後見人」を裁判所が選任します。その多くは弁護士や司法書士、行政書士、社会福祉士などから選任されます。
それに対し...
「任意後見人」は、自分が元気なうちに、パートナーや信頼できる人と、任意後見契約を結んでおくことで、自分が認知症になったあともパートナーなどに財産管理を継続して任せることが出来ます。
(※任意後見契約は公証役場で公正証書として作成する必要があります。)
公正証書遺言を作成する際公証役場に行きますので、財産管理委任契約と任意後見契約も同時に公証役場で作成すると生前の対策は非常に良いかと思います。
死後事務委任契約
これは死亡後、本来親族がすべき下記のような事務について、事実婚や内縁のパートナーへ事前に委任しておくという契約です。
死亡届、火葬許可証、喪主として葬儀手配、納骨、散骨その他の事務手続きを全て契約書として作成しておきます。
亡くなられた方にご親族がいる場合は、病院・行政など、やはり親族が優先となる場合がありますので、パートナー様の権限を明確にしておくことで他のご親族の負担を軽減することも出来ます。
遺言書を作成するうえで注意すべきこと
遺留分を考慮した遺言書作成の重要性
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる権利(財産の割合)を指します。
事実婚・内縁の妻や夫に遺産を残す場合、パートナーに実子や兄弟姉妹などの法定相続人がいる場合は、その方々の遺留分割合を考慮した遺言書を作成することが大切ですし、その配慮をすることで後に起こるトラブルを避けることが出来るかもしれません。
それぞれのケースにもよりますが、遺言書作成時には、遺留分をしっかりと考慮することが求められます。
相続人間のトラブルを防ぐための工夫
相続人間のトラブルを防ぐためには、遺言書の作成だけでなく、相続が発生する以前から、お互いの親族や家族間でのコミュニケーションが非常に重要です。
特に事実婚や内縁関係であれは、中にはお互いの親族との関係が良好とはいえないケースもあるかもしれません。
難しい場合もあるでしょう。出来る範囲で構いません。コミュニケーションをとり、お互いの関係性を少しでもよいので理解してもらえるよう行動することも大切です。
パートナーへの遺言書を作っていること、作成の経緯や想いを事前に話せたら、誤解や争いを避けることができるかもしれません。
事実婚や内縁の妻・夫と相続の未来
①事実婚・内縁関係の法整備
事実婚・内縁関係のについては、以前に比べ少しずつ権利が認められつつあります。判例や先例などが多くなることで、それらを基にした法改正が行われる可能性も高くなります。
ただ現時点においてはまだ十分とは言えず、事実婚や内縁関係であることの権利を、それぞれの場面において、積極的に証明し主張するためには、今回ご紹介したような法律上の手続きを利用するしかありません。
必要に応じて、少し先のことを見据えて、お互いで話し合いをするところから、まずは始めてみると良いかと思います。
②夫婦のかたち、家族のかたちを尊重し、思い、配慮する
現在、事実婚や内縁の関係であることは、様々な理由や考え方もありますが、そのひとつひとつが最大限に尊重されるべきことです。
しかしながら、法整備や制度自体が時代に追い付かないことも事実で、それゆえ、もしその「かたち」を選んだことによるリスク要素を少しでも軽減できる方法として、前述したような公正証書などの書類を作成しておくことは、その作成過程においても、お互いの理解や信頼も深まりますし、同時に、お互いの両親やご家族にとっても、ひとつの安心感としての「カタチ」を手に入れられる方法ではないかと思います。
パートナーやその周りのことを思いやり、少しの配慮の気持ちを持つことは円満な相続には大切なのかもしれません。
弊所、福岡県飯塚市の行政書士あきつ事務所では遺言書や相続手続きに関するご相談を受け付けております。
もしご不安なことがございましたら、お電話、お問合せメール、インスタグラムDMなどよりお気軽にお問合せくださいね。
・行政書士あきつ事務所
行政書士 光野 肇 ( mitsuno hajime )
TEL:090-8621-9966 Mail : contact@akitsu-office.com